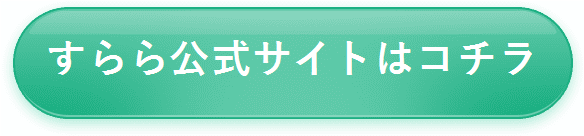すららは不登校でも出席扱いになる?なぜ?出席扱いになる理由について
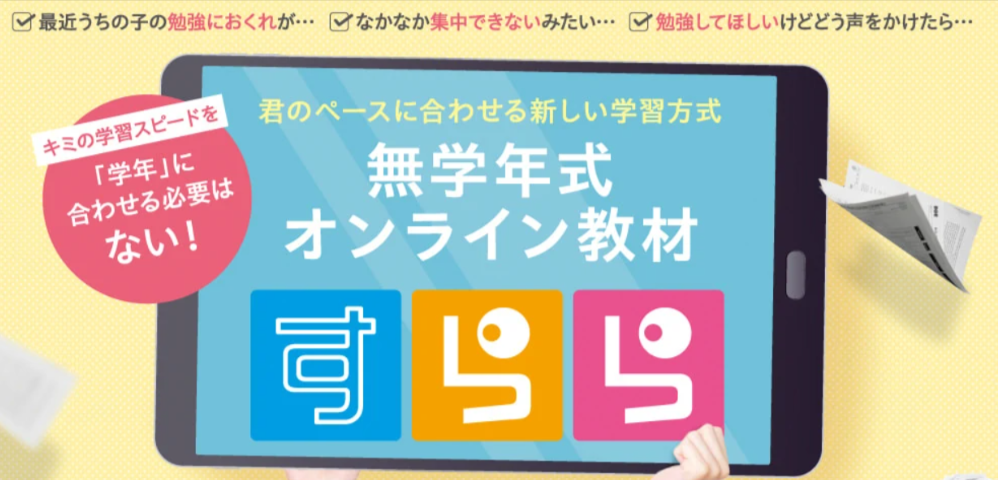
不登校の子どもを持つご家庭にとって、「出席扱いになるかどうか」は非常に重要なポイントですよね。
文部科学省では、一定の条件を満たすことで、家庭での学習も出席扱いにできる制度を設けています。
そのなかで、すららは出席認定の基準をしっかり満たしており、実際に全国の多くの学校で出席扱いとして認定された実績もあります。
ここでは、「なぜすららが出席扱いになるのか?」という理由を5つの視点からわかりやすく解説していきます。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは、学習履歴がすべてシステム上で自動記録され、可視化されます。
学習した日時・単元・理解度・正解率などのデータが細かく蓄積され、学校提出用のレポートとして出力可能です。
これらの客観的な記録があることで、学校側にとっても「出席扱い」として認めやすい根拠になります。
記録は保護者が一つひとつ作成しなくても自動生成されるため、保護者の負担も最小限に抑えられます。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、子どもの学習進捗が数値・グラフで自動的に記録されます。
これにより、学校側には「ただ勉強している」ではなく「どの単元を、どれくらい学び、どの程度理解しているのか」といった具体的な証拠を提出できます。
この客観性が、出席扱い申請において非常に有効です。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
一般的な家庭学習では、保護者が手書きで記録をつけたり、写真を提出したりするケースもありますが、すららではその必要がありません。
自動で学習記録が保存されるため、学校からも「きちんと学習していることが一目で分かる」と評価されやすいのです。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
すららは、ただの映像教材ではありません。
子ども一人ひとりに専任の「すららコーチ」がつき、継続的に学習計画を作ってくれます。
特に不登校の子どもにとっては、自分のペースに合った計画で進められることが学習継続の大きなカギになります。
さらに、無学年式の教材設計なので、学年に関係なく「苦手なところから戻る」「得意な教科は先取りする」といった柔軟な学びが可能です。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららの大きな特長は、学習管理を「保護者任せ」にしない点です。
専任コーチが学習計画の立案から見直しまでを一緒に行ってくれるため、「ただ使っている」だけでなく「継続している学習習慣」として学校に報告できます。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
子どものモチベーションや生活リズムに応じて、コーチが週単位で無理のないスケジュールを提案してくれます。
継続的なやり取りがあることで、孤立しがちな不登校の子にも安心感があります。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
不登校期間が長いと、「前の学年内容に戻って学び直したい」というニーズが出てきます。
すららなら、学年に関係なく自分のペースで復習や先取りができるので、出席扱い後の復学にもスムーズに対応できます。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
出席扱いには、家庭・学校・教材の三者連携が必要不可欠です。
すららでは、その橋渡しとなるフォロー体制も万全です。
保護者がどの書類をどう準備すればよいのか、学習報告書の書き方、学校側とのやりとりのコツまで、細かくサポートしてくれます。
すでに多くの自治体で認定実績があるため、学校側もすららの存在を知っているケースが多く、手続きもスムーズです。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
出席扱いの申請には、文科省ガイドラインに基づいた書類が必要です。
すららではその書類のテンプレートや作成例を提供してくれるため、初めての方でも安心して準備できます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
すららでは、出席扱いの申請に必要な「学習レポート」について、専用フォーマットを用意しており、コーチが提出までの流れをしっかりフォローしてくれます。
レポートには、学習の進捗・取り組み内容・時間などが自動で記録されており、保護者が手作業でまとめる必要がないのも魅力です。
また、提出のタイミングや提出先、学校側が求める情報に合わせたアドバイスも受けられるため、初めての申請でもスムーズに進めることができます。
「どう書けばいいかわからない…」と不安に思うことがあっても、コーチが寄り添ってくれるので安心ですね。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
出席扱いを目指すうえで、学校との信頼関係づくりは欠かせません。
すららでは、家庭と学校とのやり取りがスムーズに進むように、連携サポートも行っています。
例えば、担任や校長先生に提出する学習報告のフォーマット提供、説明資料の準備、報告書に記載する内容の相談など、細かな部分までバックアップしてくれます。
これにより、学校側も「何を基に判断すればいいか」が明確になり、結果として出席扱いとして認められやすくなります。
保護者一人では難しい部分を、教材側がサポートしてくれるのは心強いですね。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省のガイドラインに準拠した教材として、全国で実際に出席扱いとしての採用実績があります。
数多くの教育委員会や学校と連携し、不登校の子どもたちの学習支援に役立てられてきました。
「学校に行けない=学べない」ではなく、「自宅でもしっかり学べる」「学校とつながりを持ち続けられる」ことを実現してきた実績が、教育関係者からも高く評価されています。
こうした背景から、担任や校長先生がすららを見たときに「この教材なら出席扱いとして認めても問題ない」と判断してくれやすいのです。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、北海道から沖縄まで、全国のさまざまな自治体や学校と連携し、不登校支援の一環として導入されてきました。
そのため、教育現場でもすららの名前を知っている先生が多く、教材の内容や実績について理解があるケースも少なくありません。
これにより、出席扱いの申請を行った際にも、教材の信頼性をスムーズに伝えることができるというメリットがあります。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは公式に「不登校対応教材」として認められており、すらら自身のサイトでもその情報がしっかり記載されています。
教材内容も、学校教育で学ぶべき範囲を網羅しており、定期テスト・受験対策にも対応しています。
そのため、「単なる補習」ではなく、「学校教育と同等の学習ができる教材」として、多くの自治体や教育機関からも信頼されています。
こうした“公的な後ろ盾”がある点も、出席扱いを目指す家庭には大きな強みになります。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いとして認められるための大前提に、「家庭での学習環境が、学校での教育と同等の水準にあるか」という基準があります。
すららは、国語・数学・理科・社会・英語など、主要5教科を網羅したカリキュラムがあり、しかもそれが文部科学省の学習指導要領に準拠して作られています。
さらに、学習の成果や進捗をリアルタイムで可視化・記録し、フィードバックまで行えるシステムがあることで、教育の質としても“学校に準ずる”と判断されやすいのです。
「ただやっている」だけでなく「学んでいることを証明できる」という点が、すららの大きな強みとなっています。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららのカリキュラムは、小学1年生から中学3年生までの内容をカバーし、すべてが学習指導要領に基づいて作られています。
そのため、「学校で学ぶべき内容がちゃんと学べている」と学校側が判断しやすいのです。
この点は、出席扱いの申請時にとても重要で、「独自教材」や「非認定の学習アプリ」では得られない信頼性がすららにはあります。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、単に学習を進めるだけでなく、その結果や理解度が自動で記録され、講師やコーチからのフィードバックが受けられます。
この「評価と指導の循環」がしっかり機能しているため、学校側も「教育的価値が高い」と認識しやすいのです。
学習の成果が定量的・視覚的に残る仕組みがあるからこそ、「自宅での学習=学校と同等」として判断される根拠となります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法の流れ紹介
不登校でもすららを活用することで「出席扱い」にできる制度があることをご存じですか?文部科学省は、一定の条件を満たした家庭学習に関して、出席扱いが可能であると認めています。
すららはこの条件を満たす教材として、全国の学校で実際に出席扱いの認定を受けた実績が多数あります。
ただし、この制度を活用するには、学校とのやりとりや書類の提出など、一定の手続きが必要です。
ここでは、すららを使った出席扱い申請の具体的な流れと注意点を、ステップごとに詳しくご紹介していきます。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱い制度を活用するうえで、最初にすべきことは「担任または学校への相談」です。
不登校になっている期間にどのような学習をしているかを共有し、「すららでの学習を出席扱いとして申請したい」という意思を伝えましょう。
文部科学省のガイドラインに基づく出席扱いは、最終的に学校長の判断に委ねられます。
そのため、担任や学年主任としっかり話をし、学校側に協力を仰ぐ姿勢が大切です。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
申請には、すららでの学習記録を提出するだけでなく、「申請書」「学習計画書」などが必要になることがあります。
また、学校によっては独自のフォーマットや補足資料の提出を求められる場合もあるため、最初の相談時に「必要な書類一覧」「提出先」「締切」などをしっかり確認しておくことがスムーズな手続きにつながります。
疑問があれば、すららコーチにも相談できるので安心です。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
出席扱いの申請では、必ずしも診断書が必要というわけではありません。
ただし、不登校の理由が「心身の不調」や「発達障害・情緒面の課題」などの場合、学校側が判断材料として診断書を求めることがあります。
教育委員会が関与するケースでは、客観的な証拠として診断書の提出がほぼ必須となることも。
必要かどうかは学校に確認しつつ、万が一に備えて早めに準備しておくと安心です。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
「不登校=診断書必須」というわけではありませんが、出席扱いをよりスムーズに進めたい場合には、診断書があったほうが有利に働くことがあります。
特にメンタル面の不調や発達の特性が背景にある場合は、診断書の提出によって学校側の理解を得やすくなるケースが多いです。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書には、「現在の状態(通学困難な理由)」と「家庭学習による学習継続の必要性」が記載されていると、出席扱いの申請がスムーズになります。
かかりつけの小児科や心療内科に相談して、趣旨を説明すれば対応してくれることが多いです。
必要な文言などが不明な場合は、すららや学校からサンプルをもらうのも一つの方法です。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いの核となるのが、すららでの学習記録です。
タブレット上に記録された学習時間・内容・正答率などのデータは、学校提出用のレポートとしてPDF形式で出力できます。
このデータを担任や校長先生に提出し、実際に「どのくらい学習しているか」を客観的に示すことで、出席扱いの判断材料として活用されます。
提出前には、すららのコーチが必要な資料やポイントをアドバイスしてくれるので安心です。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
学習進捗レポートには、日付ごとの学習時間、単元別の正答率、累計学習時間などがまとめられており、視覚的に成果が伝わる形式になっています。
これを担任または校長に提出することで、「ただ家にいるのではなく、学習をしっかり継続している」という証明になります。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱いの申請書類は、多くの場合学校側が作成しますが、家庭側が補足情報を提供したり、申請理由を書いたりするケースもあります。
すららを活用している場合は、使用開始日や学習スタイル、すららの学習内容について簡単に記入できるよう準備しておくと、先生との連携もスムーズになります。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
すべての書類がそろい、担任との協議が完了すると、最終的には学校長の判断によって出席扱いとなるかが決まります。
一部の地域やケースでは、教育委員会への報告や申請が必要な場合もあります。
その際も、学校が窓口となって対応してくれることがほとんどなので、焦らず学校との連携を保ちながら進めましょう。
保護者としては「協力的であること」「適切な情報提供をすること」がスムーズな承認のカギになります。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
文部科学省のガイドラインでは、「出席扱いの最終決定権は学校長にある」とされています。
担任や学年主任とのやりとりを経て、校長が「適切な学習がされている」と判断した場合、正式に出席扱いとして記録されます。
すららはその条件をクリアしやすい教材であるため、実際に承認される事例が増えています。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、学校だけでなく教育委員会への申請や報告が必要なケースもあります。
この場合でも、学校側が主導で申請を進めてくれることが多いので、保護者は必要な情報提供と書類への署名など、サポート的な役割を担えばOKです。
無理に単独で動こうとせず、学校との連携を第一に考えると安心して進められます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて解説
すららを使って自宅学習を継続し、出席扱いとして認めてもらえると、実は多くのメリットがあります。
単に「欠席扱いにならない」だけでなく、その先の進学や子どもの心の安定、さらには保護者の精神的なゆとりにまで影響してきます。
不登校という状況は、子どもだけでなく家庭全体に大きな不安をもたらしますが、出席扱い制度を活用することで、学びの遅れや将来への不安を和らげることができます。
ここでは、出席扱いが認められることで得られる具体的なメリットを3つの視点からご紹介します。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
出席扱いが認められると、「欠席」ではなく「出席」として記録されるため、通知表や内申点への影響が最小限に抑えられます。
中学校・高校進学を控えているお子さんにとって、これは非常に大きな意味を持ちます。
特に中学生は、内申点が高校入試の合否に直結するため、出席日数を確保できるだけでも将来の選択肢が大きく広がります。
さらに、「学習を続けている」という事実そのものが先生や進学先からの信頼にもつながり、不登校=怠けではないという正しい理解を得ることにも貢献します。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
学校に行けていなくても、「出席扱い」で記録されれば、授業への出席状況に関する評価は下がりにくくなります。
実際にすららを活用して学習し続けていれば、学習の取り組み姿勢として高く評価されるケースもあります。
日数が不足して内申が落ちるリスクを避けられるのは、受験期には大きな安心材料です。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席日数がしっかり確保され、学習も継続しているという実績があることで、志望校の幅が広がります。
「不登校だから…」と選択肢を狭める必要はありません。
推薦入試や調査書が重要視される学校にも対応できるため、子ども自身のモチベーションアップにもつながります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校が長引くと、「みんなは進んでいるのに自分は遅れている」という焦りや不安にとらわれやすくなります。
しかし、すららを活用すれば、無学年式のカリキュラムで自分のペースで学び直すことができ、「遅れた分を取り戻せる」という実感が得られます。
また、日々の取り組みがデータとして見えるので、「頑張っている自分」を確認できることが、自己肯定感の維持にもつながります。
この感覚は、学習だけでなく、再登校や新たな挑戦への原動力にもなっていきます。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
学校の授業についていけないことが不安で登校できないお子さんにとって、「家でちゃんと学べている」という実感は大きな支えになります。
すららは、基礎から応用までの範囲を網羅しており、わからない部分を繰り返し学べる設計なので、授業の遅れを恐れることなく、自信を持って学びを続けられます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
「どうせ自分はできない」「また失敗する」といった思い込みが強くなる前に、すららのような“ほめて伸ばす”教材で小さな成功体験を積み重ねることは、子どもの心の安定にもつながります。
できたことが目に見える=自己肯定感が下がりにくくなる。
それが、長期的に見て最も大きなメリットになるかもしれません。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを支える親にとって、「このままで大丈夫なのか」「将来はどうなるのか」という不安は計り知れません。
でも、すららで出席扱いが認められるようになれば、「この子は家でしっかり学んでいる」という安心感が生まれます。
さらに、すららには専任のコーチがついてくれるため、保護者ひとりで悩みや学習の方向性を抱え込む必要がなくなります。
学校との連携もサポートしてくれるので、親の精神的な負担は確実に軽減されます。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
家庭だけでがんばるのではなく、すららのコーチや学校の先生とチームで取り組めるのが大きなポイントです。
「ひとりでなんとかしなきゃ…」というプレッシャーから解放され、安心してお子さんを見守れる環境が整います。
親が落ち着いていれば、子どもにもその安心感は伝わっていきますよ。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための重要な注意点について解説
すららを活用して不登校のお子さんの出席扱いを目指す場合、正しい方法で進めることでスムーズに認定されるケースが多くあります。
ただし、いくつかの注意点をおさえておかないと、学校側とすれ違ったり、書類が不備だったりして、せっかくの努力が評価されないこともあるのが現実です。
ここでは、すららを活用して出席扱いを受けるために必ず知っておきたい3つの注意点について、具体的な対応方法も交えてご紹介します。
申請を成功させるための下準備として、ぜひチェックしてみてくださいね。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いの最終判断は校長先生に委ねられています。
そのため、担任の先生だけに話すだけでは不十分な場合があります。
すららが文部科学省のガイドラインに基づいて作られた教育教材であること、他の多くの自治体や学校でも出席扱いとして認定されている実績があることを、丁寧に伝えることが大切です。
教師側がその場で判断できないこともあるため、教頭先生や校長先生に早めに直接相談するのが望ましいです。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
「すらら」という名前を知らない先生もいる可能性があります。
そのため、「文科省の出席扱い制度の基準を満たしている教材です」と一言添えて説明することで、理解を得られやすくなります。
できればすららの公式サイトに記載されている文部科学省のガイドラインとの関連情報もあわせて共有すると安心です。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
口頭だけでなく、実際の資料を見せることが説得力を高めます。
すららの公式パンフレットや学習記録のレポートなどを一緒に持参すると、学校側も「これはしっかりした教材なんだな」と理解してくれやすくなります。
また、担任の先生から上に話がうまく伝わらないこともあるため、最初から教頭先生・校長先生に直接相談するのが安心です。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の理由によっては、家庭学習をしていても出席扱いにならないケースもあります。
特に「精神的な理由」や「継続的な体調不良」によって通学が困難な場合は、医師の診断書や意見書が求められることが一般的です。
すべてのケースで必要というわけではありませんが、診断書があることで学校側の納得度が高まり、出席扱いが認められる可能性が上がります。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
たとえば、不安障害・適応障害・ASD・HSPなどの診断を受けているお子さんの場合には、通学が難しい正当な理由が必要とされ、医師の意見が重視されます。
学校によっては診断書が申請の必須条件として定められている場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書の発行をお願いする際は、「出席扱いの申請をしたいので診断書をお願いできますか」と具体的に伝えることが大切です。
医師はその目的が分からないと、ただの通院記録のような内容になってしまうこともあります。
すららで学習していることや、家庭での取り組み内容も合わせて伝えると、より実用的な診断書を作成してもらえる可能性が高まります。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
「子どもは家庭で意欲的に学習を継続しており、登校困難であるが学習環境は整っている」といった内容が診断書に書かれていると、学校側も出席扱いを認めやすくなります。
医師に家庭での学習状況をしっかりと伝え、できるだけ前向きな言葉で記載してもらうようにしましょう。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いの条件としては、「学習の内容・時間が、学校教育と同等であること」が重要視されます。
つまり、ただの自習や参考書学習ではなく、明確に「学校の授業内容に準拠している教材かどうか」がチェックされます。
その点、すららは文部科学省の学習指導要領に沿ったカリキュラムが組まれているため、十分に要件を満たします。
ただし、学習時間が極端に少ない場合や、学習記録が残っていない場合は認められにくくなるため、日々の記録の蓄積は重要です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
子どもが自由に選んだ勉強を少しだけやっている、という状態では学校側も出席扱いとは判断しません。
学習内容が国語・数学・理科・社会・英語など主要5教科にわたっており、学習進捗がレポートで可視化できるかどうかが鍵になります。
すららで日々の記録をしっかりと残し、学校にも共有することが大切です。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いが認められるためには、家庭での学習時間も「学校で授業を受けるのと同程度」であることが求められます。
文部科学省のガイドラインでは明確な時間数は示されていませんが、目安として1日あたり2〜3時間程度、週に5日ほどの学習を継続していると好ましく判断されるケースが多いです。
すららは、短時間×高効率の設計なので、無理のない範囲でこの基準をクリアしやすいのが特長です。
ただし、やみくもに長時間やるのではなく、毎日のリズムに組み込み、安定して継続することが大切です。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
「国語・数学・英語」などの主要3教科だけに偏ってしまうと、出席扱いの要件を満たさない場合があります。
学校での学習は5教科(国・数・英・理・社)をバランスよく進めるのが基本であり、家庭学習でもそれに準じた内容が求められます。
すららでは3教科・4教科・5教科コースが選べますが、出席扱いを見据えるのであれば、できるだけ全教科に取り組める環境を整えるのがおすすめです。
バランスよく取り組む姿勢が、学校からの信頼にもつながります。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いの申請後も、学校との定期的な連絡は非常に重要です。
「学習が継続されているか」「進捗はどれくらいか」といった情報を、担任の先生や校長先生にこまめに共有することで、信頼関係が生まれやすくなります。
すららでは学習記録のレポートを簡単にダウンロードできるので、月に1回程度、学校に提出することを習慣にするのがおすすめです。
また、必要があれば家庭訪問や面談にも前向きに対応し、「子どもが家庭で頑張っている」ことを具体的に伝える機会を持ちましょう。
申請が通った後も、学校との連携が出席扱いの継続に欠かせません。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
文部科学省のガイドラインでも、「家庭と学校の連携」が強調されています。
単に学習しているだけでなく、その内容・成果・意欲を学校側が把握していることが大切です。
報告の頻度や方法は学校と相談し、無理のない範囲で共有を心がけましょう。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららの学習管理画面から出力できる「学習記録レポート」は、出席扱いの申請・維持に非常に便利です。
月1回程度、レポートを印刷またはPDFで提出することで、継続的に取り組んでいる証明になります。
提出先やタイミングは担任の先生と相談しておくとスムーズです。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校側が子どもの様子を直接確認したいと考えることもあります。
家庭訪問や面談の依頼があった場合は、前向きに対応し、学習環境や本人の様子を見てもらうことで、より安心して出席扱いを認めてもらえる可能性が高まります。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
形式ばらず、気軽なメールや電話で定期的に報告するだけでも十分です。
「〇〇の単元を終えました」「今週は体調が良く、1日2時間ほど学習できました」など、具体的な内容を簡単に伝えることで、信頼関係を築くことができます。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
出席扱いの判断は基本的には学校長に任されていますが、自治体によっては教育委員会の承認が必要なこともあります。
特に学区外からの申請や、長期間に及ぶ場合などは、教育委員会とのやり取りが発生するケースもあります。
こうした場合も、学校としっかり連携し、指示を仰ぎながら対応すれば心配ありません。
必要書類や提出方法については、すららのサポートやコーチからもアドバイスが受けられるので、安心して進めていきましょう。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会に提出する場合も、基本は学校経由で行われます。
必要な資料(学習記録・診断書・意見書など)を学校側に渡し、内容を確認してもらいながら準備を進めると安心です。
自治体ごとに求められる書類が異なる場合もあるので、不明点はすぐに学校に確認するようにしましょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを解説
出席扱いの制度は、文部科学省のガイドラインによって認められた仕組みではありますが、実際の運用には学校ごとの判断が大きく影響します。
そのため、ただ形式を整えるだけではなく、「この子には出席扱いがふさわしい」と学校側に納得してもらうための工夫が大切です。
ここでは、すららを使って出席扱いを申請する際に、実際に承認された家庭が意識していた成功ポイントをご紹介します。
前例の紹介や本人の意欲の伝え方、継続可能な学習計画の立て方など、すぐに実践できる内容ばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
出席扱い制度はまだまだすべての学校に浸透しているとは言えず、「初めて聞いた」という先生も少なくありません。
そんなときに効果的なのが、「他の学校でもすららを使って出席扱いが認められた」という前例を示すことです。
すららの公式サイトには、実際に出席扱いが認められた事例が多数掲載されており、これをプリントアウトして学校に持参するだけで、「前例があるなら安心」と受け入れてもらえる可能性が高まります。
特に慎重な学校ほど、客観的な情報に安心感を持つので、資料の準備は非常に有効です。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
全国には、すららを使って出席扱いが認められた学校の実績が多数あります。
「他の公立中学でも同じように申請されている」と伝えることで、学校側も制度の理解が進みやすくなります。
すららの実績を学校に伝えることは、申請の信頼度を高める重要なアクションのひとつです。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すらら公式サイトの「出席扱い制度に関するページ」や「導入校実績紹介ページ」は非常に説得力があります。
プリントアウトして学校側に渡すことで、先生や校長先生の認識が深まり、より前向きに受け取ってもらえる可能性が高くなります。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いを判断するうえで、学校側が特に重視するのが「本人に学習の意思があるかどうか」です。
たとえ教材や環境が整っていても、本人のやる気が伝わらなければ、継続性への不安から承認をためらわれることもあります。
そこでおすすめなのが、本人が書いた学習の感想や目標を提出することです。
「今日は英語を頑張った」「来週は理科を集中してやる」など、シンプルな内容でOK。
さらに、面談の際に本人が直接「勉強を続けたい」と伝えると、より強い印象を残すことができます。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
子どもが「今、どんな気持ちで勉強しているか」「どんなことができるようになったか」などを自分の言葉で書いたメモは、学校側の心を動かす力があります。
形式ばった作文でなくても大丈夫。
短いメモや日記形式でOKです。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
本人が「すららで勉強している」「学校に戻りたい気持ちもある」といった気持ちを自分の声で伝えられると、担任や校長先生の受け止め方も大きく変わります。
やる気を示すことが、出席扱いの後押しになります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いが認められるには、単発の取り組みではなく「継続して学習している」ことが不可欠です。
ですが、無理なスケジュールで始めると途中で挫折してしまい、結果的に承認が取り消されたり、続けられなくなるリスクもあります。
そこで重要なのが、本人の体調や性格、生活リズムに合わせた現実的なスケジュールを立てることです。
すららでは、専任の「すららコーチ」が学習計画の立案をサポートしてくれるため、一人で抱え込む必要はありません。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
「1日30分×3回」や「好きな教科から始める」など、本人が無理なく続けられる方法を優先して計画することで、継続しやすくなります。
週単位での目標設定もおすすめです。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららコーチは、子どもの特性に合わせたアドバイスができるプロフェッショナルです。
「今の状態で無理なくできるペースはどれくらいか」「どこから始めると成功体験を得られやすいか」など、細かく相談できます。
ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する
出席扱いを申請するうえで、最も心強い味方となるのが「すららコーチ」です。
学習状況の記録を提出する際のレポート作成方法や、出席扱い制度に関する知識、教育委員会や学校への伝え方など、実務的な部分でも徹底的にサポートしてくれます。
また、子ども本人のやる気を引き出すための声かけや、保護者へのメンタルサポートも行ってくれるので、「親子で抱え込まない学びの仕組み」が実現します。
出席扱いを目指すのであれば、コーチの力を遠慮なく借りましょう。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
学習記録をどうまとめるか、どの情報を強調すべきか、といった細かい部分までアドバイスしてくれるのがすららコーチの強みです。
学校提出用のレポートも一緒に確認してくれるため、「これで大丈夫かな」と不安になることもありません。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミ・評判を紹介します
不登校の子どもを持つ保護者にとって「自宅学習が学校の出席扱いになるのかどうか」は大きな関心事です。
すららは文部科学省が推進するICT教材として認められており、学校や教育委員会との連携次第で出席扱いになるケースがあります。具体的には、学校側が「学習の記録」「取り組み状況」を確認できるようにしておけば、出席日数にカウントされる場合があるのです。
実際の口コミでも「すららで学習した内容を先生に報告して出席扱いになった」「自宅で安心して勉強できるので不登校の子どもも前向きになった」という声が寄せられています。
一方で、学校ごとの判断に左右されるため、必ずしもすべてが出席扱いになるわけではありません。
それでも「安心して学習を続けられる環境が整った」「学習習慣がついて自信が戻ってきた」というポジティブな体験談は多く、不登校の子どもや家庭にとって心強いサポートとなっています。
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問と回答
すららを利用している保護者の方からよく寄せられる質問のひとつに「不登校でも出席扱いになるのですか?」というものがあります。
結論から言うと、条件を満たせば出席扱いになるケースがありますが、必ずすべての学校で認められるわけではありません。文部科学省の通知では、ICT教材を活用した家庭学習も出席扱いの対象となる可能性があるとされています。
ただし、実際に出席扱いになるかどうかは学校ごとの判断に委ねられており、担任の先生や教育委員会との相談が必要です。
口コミでは「校長先生に相談して承認された」「学校が柔軟に対応してくれて安心した」という前向きな声もあれば、「学校側の理解が得られず出席扱いにならなかった」というケースも見られます。すららを利用することで学習習慣を保ちつつ、出席扱いになる可能性を広げることは十分に期待できますが、最終的には学校との連携が大切です。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すららはうざい」といった口コミが見られる理由には、主に保護者や生徒の期待値とのギャップが関係しています。
例えば「思ったより続けられなかった」「サポートが合わなかった」「料金が高く感じた」といった声が一部で見られます。
ただし、それらはごく一部のケースであり、実際には「自分のペースで進められて安心」「子どもが学習を楽しんでいる」といったポジティブな口コミの方が圧倒的に多いのも事実です。
学習スタイルやサポート内容が個人に合うかどうかは使ってみないと分からないため、まずは無料体験などで雰囲気をつかむのがおすすめです。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには「発達障害専用コース」という明確な名称はありませんが、ADHD、ASD、LD(学習障害)などに配慮された設計が特徴です。
料金は一般の受講生と同じで、障害の有無によって割引されることはありません。
しかし、教材設計がユニバーサルデザインになっており、視覚的・聴覚的なサポートや短時間集中型の学習構成が用意されています。
また、すららコーチが子どもの特性に合わせた学習計画を提案してくれるため、個別最適な学習支援が受けられる点は大きな魅力です。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららは文部科学省のガイドラインに準拠した教材として、全国の多くの学校で「出席扱い」として認められています。
必要な条件としては、学習内容が学校の授業に準じていること、学習時間が確保されていること、そして家庭と学校間で学習状況が定期的に共有されていることが挙げられます。
すららでは、学習記録やレポートが自動で作成されるため、学校へ提出する資料も準備しやすく、出席扱いの手続きを進めるうえで非常に有利です。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは定期的に入会キャンペーンを実施しており、専用のキャンペーンコードを入力することで、入会金無料や月額料金割引などの特典を受けられます。
キャンペーンコードは、すらら公式サイトや紹介サイト、メールマガジンなどで案内されることがあります。
利用方法は簡単で、入会申込時にキャンペーンコードを入力欄に記入するだけでOKです。
使用期限がある場合や、他の特典と併用不可のケースもあるため、事前に適用条件を確認しておきましょう。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを退会するには、「解約」と「退会」の2ステップを理解することが大切です。
「解約」とは毎月の利用料を止めることで、これは電話での手続きが必要です。
メールやWebフォームでは受け付けていないため、サポートセンター(すららコール)に連絡し、登録情報の確認を行ってから解約日を指定します。
「退会」はアカウント情報や学習履歴などを完全に削除する手続きです。
解約時に「退会も希望」と伝えれば、まとめて対応してくれます。
なお、解約だけでも料金の請求は止まるので、再開を視野に入れて情報を残す方も多いです。
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららは非常にシンプルな料金体系を採用しており、基本的には「入会金」と「月額料金」だけで利用できます。
教材費やシステム利用料などの追加費用は一切かかりません。
また、学習に使用するタブレットやパソコンもレンタルではなく、家庭で用意した端末でOKなので、端末代が別途請求されることもありません。
ただし、インターネット環境が必須となるため、自宅の通信費やWi-Fiの整備は必要になります。
見えないコストが少ないため、費用面でも安心して利用できます。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららでは、受講者ごとにIDが発行され、学習進捗や成績データを個別に管理するため、1人分の受講料で兄弟が一緒に使うことはできません。
兄弟で使う場合は、それぞれに契約が必要ですが、2人目以降の入会金が割引になるキャンペーンが適用されることもあります。
別々のアカウントを持つことで、AIによる弱点分析や学習スケジュールも個別対応が可能になり、兄弟それぞれのペースで無理なく学習できる環境が整います。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには英語学習コンテンツがしっかり含まれています。
英語初心者でも取り組みやすいように、アニメーションと音声を組み合わせた視覚・聴覚で学べる内容になっており、フォニックスや基礎単語から英文法の初歩まで幅広く学べます。
無学年式なので、小学校低学年でも上のレベルに挑戦できたり、逆に理解が不十分な部分を下の学年に戻って復習することも可能です。
楽しく学べる設計で、英語に対する苦手意識を持たせにくい点も魅力です。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららのコーチ(すららコーチ)は、受講生一人ひとりに対して学習計画の提案や学習進捗のチェック、つまずきへのフォローなどを行ってくれるサポーターです。
特に発達障害や不登校のお子さまには、それぞれの特性や生活リズムに応じた提案をしてくれるため、「何から始めればいいか分からない」という場合でも安心です。
また、保護者への相談対応も行っており、学習に関する悩みだけでなく、声かけや習慣づけのアドバイスまで寄り添って対応してくれます。
孤立感を感じがちな保護者にとっても、大きな支えになります。
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材との違いを比較しました
家庭学習をスタートするうえで、「出席扱いになる教材がいいけど、費用も気になる…」という保護者の方は少なくありません。
すららは不登校対応に強いとよく言われますが、実際に他のタブレット教材と比べてどうなのでしょうか?この記事では、月額料金、サポート体制、出席扱いの手続きのしやすさといった観点で、すららと他社教材を比較してみました。
コスパ重視だけど制度面もしっかりしたい、という方にぴったりの内容です。
最終的に「我が子にとって一番合う教材」が見つかるヒントになればうれしいです。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。
|
16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・注意点・申請手順まとめ
不登校の子どもがすららで学習を続けているご家庭にとって、「出席扱いを申請したいけど、どう進めればいいの?」という疑問は切実ですよね。
この記事では、すららがどのように出席扱い対象になるのか、学校側にどう説明するか、具体的にどんな書類が必要なのかまで、細かく整理しています。
また、申請時に「ここだけは気をつけたい」という注意点や、スムーズに承認をもらうための工夫もご紹介。
実際に申請を検討しているご家庭にとって、頼れるガイドになるはずです。