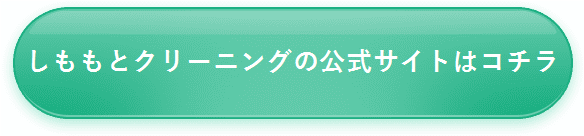しももとクリーニングに保管サービスはある?布団保管を行っていない理由とその背景を解説

最近では、布団をクリーニングしたあとにそのまま預かってくれる「保管サービス」がある業者も増えてきましたよね。
でも、しももとクリーニングではあえてその保管サービスを提供していません。
それには、ふとんと真剣に向き合ってきたからこその、確かな理由があります。
このページでは、なぜしももとクリーニングが保管を行っていないのか、その考え方やこだわりについて詳しくお伝えしていきます。
布団を長く気持ちよく使いたい方にとって、大切な考え方が詰まっていますので、ぜひ参考になさってください。
理由1・ クリーニング後すぐに最高のコンディションで使ってほしいから
リナビスが保管のみを受け付けていない理由のひとつは、クリーニング後の衣類を「最高のコンディションで、できるだけ早く使ってほしい」という思いがあるからです。
せっかく丁寧に仕上げた衣類を、長期間放置してしまうと、どうしても素材に負担がかかったり、保管中の環境によっては変化が生じることがあります。
リナビスでは、クリーニングの仕上がり直後がもっとも美しい状態であると考えていて、そのまま気持ちよく着用してもらえるようなタイミングで届けたいと考えています。
プロの手による仕上がりをそのまま実感してもらうためにも、保管だけという使い方はおすすめしていないんですね。
だからこそ、保管はあくまで「次のシーズンに備えるため」のオプションとして扱われているのです。
仕上がった時点がふとんのベストコンディション
しももとクリーニングでは、布団の仕上がり状態を何よりも大切にしています。
ふとんというのは、洗い立て・乾き立てのタイミングがもっともふっくらとしていて、衛生的にも清潔な状態です。
この「今すぐ寝転びたい」と感じるような最高のコンディションで、ぜひご家庭で使っていただきたいという思いから、保管ではなく「即お届け」を選んでいるのです。
仕上がった直後のふとんは、まさに“おろしたて”のような気持ち良さ。
そのベストな状態を味わってもらうために、スピード感のある配送にもこだわっているのが特徴です。
保管中に湿気やニオイがつくリスクを考えると、できるだけ早く自宅で管理した方がいい
保管サービスというのは便利に見えますが、実は布団にとっては負担になることもあるのです。
長期間、倉庫での保管となると、たとえ温度や湿度が適切に管理されていても、微細な湿気や倉庫独特のニオイが布団に移ってしまうリスクがあります。
そうなれば、せっかくクリーニングできれいになった布団が、思ったほど気持ち良く使えないという結果にもなりかねません。
しももとクリーニングでは「本当に気持ちよく眠れること」を大事にしているからこそ、保管せずにすぐお届けするスタイルをとっています。
理由2・保管によるふとんへの負担を避けたいから
ふとんのようなかさばる寝具は、保管方法ひとつで品質に大きな差が出るデリケートなアイテムです。
リナビスでは、ふとんのクリーニングも取り扱っていますが、保管に関しては慎重な姿勢をとっていて、基本的に保管のみのサービスは提供していません。
というのも、ふとんは圧縮や積み重ねの状態が悪いと中綿が偏ってしまったり、型崩れや通気性の低下を招く恐れがあるからなんです。
せっかくクリーニングでふかふかに蘇ったふとんも、長期保管の状態が悪ければ、その質感が失われてしまうかもしれません。
そうしたリスクを避けるためにも、リナビスでは自宅での保管を推奨し、保管だけのサービスはあえて提供していないのです。
ふとんを大切に扱いたいという姿勢が伝わってきますよね。
長期間、倉庫で保管していると温度・湿度管理が万全でもふとんのふくらみや質感に影響が出るリスクがある
布団は見た目以上に繊細で、保管状態によってコンディションが大きく左右されるものです。
たとえ高性能な空調設備を使った倉庫であっても、圧力や重なり、わずかな環境の変化などにより、ふくらみが減ってしまったり、表面の質感が損なわれる可能性があります。
しももとクリーニングでは、そうした“わずかな変化”すら布団にとってマイナスだと考えています。
だからこそ、最高の状態でクリーニングを終えたら、なるべく早くお客様の手元にお届けしたいという想いがあるのです。
クリーニング品質にとことんこだわっているから保管による品質劣化の可能性を極力避けたい
しももとクリーニングの強みは、ひとつひとつの布団を丁寧に扱うその品質にあります。
中綿の状態や肌触り、ふっくら感など、どれもこだわり抜いた仕上がりをお届けするために、機械まかせにせず人の手と目で確認しながら作業が行われています。
そうした丁寧な工程を経て仕上がった布団を、保管によって劣化させてしまうのは本末転倒です。
だからこそ、品質を守るために「保管しない」という選択をしているのです。
この方針には、すべての布団に対する真剣な愛情が詰まっています。
理由3・他人のふとんと一緒に保管するリスクを避けたいから
保管サービスでは、複数の利用者の衣類や寝具を一括で保管することが一般的ですが、リナビスではその「混在によるリスク」に敏感です。
とくにふとんなどの大きなアイテムは、保管スペースの都合上、他人のふとんと一緒に積まれたり、並べられたりすることがありますが、そこに衛生的な懸念が生じる場合もあるんです。
リナビスでは、利用者ひとりひとりの大切な衣類や寝具を安全に守ることを最優先としているため、そうした混在保管のリスクを徹底的に避けたいという方針があります。
そのため、ふとんの保管のみサービスは行っておらず、保管を希望する場合も清潔な状態を保ちやすい衣類などに限定しているのです。
この配慮こそが、信頼につながっている理由のひとつなんですよ。
他人の布団を一緒に保管することでダニ・カビ・雑菌のリスクがある
保管サービスというと便利そうに思えますが、実は“他人の布団と一緒に保管する”という見落とされがちなリスクが潜んでいます。
どれだけクリーニングされた状態でも、完全に無菌というわけではなく、倉庫内で複数の布団が近い状態で置かれることで、ダニや雑菌が移る可能性はゼロではありません。
湿気が残っていたり、菌の元になる要素がひとつでも混ざっていれば、それが全体に影響を及ぼすこともあります。
しももとクリーニングでは、こうした見えないリスクからお客様の布団を守りたいという想いがあり、だからこそ「保管しない」という方針をとっているのです。
他人の匂いが移るリスクがある/肌に直接つくものだからこそ保管は厳重にしてほしい
布団は毎日、肌に直接触れるものだからこそ「衛生面」や「におい」には敏感になりますよね。
いくら倉庫が清潔で温湿度が管理されていても、他人の布団と近い距離で保管されていれば、わずかな香料や生活臭が移ることがあります。
それが気になる方にとっては、大きなストレスになってしまうのです。
しももとクリーニングは、この“気になるかもしれない”を絶対に見逃さない会社です。
だからこそ、保管は各家庭でしてもらうというスタンスをとり、お届けした時点での「最高の状態」が長く続くよう、最善の品質で返してくれるのです。
理由4・保管コストを価格に転嫁したくないから
リナビスは、サービスの品質を維持しながらも、利用者が納得できる価格設定を大切にしている宅配クリーニングです。
もし「保管のみ」サービスを行った場合、温度・湿度を管理した施設の使用や管理人員の確保など、相応のコストが発生してしまいます。
それを価格に反映させると、結果的に利用者の負担が増えることになってしまうんですね。
リナビスでは、必要な人だけが保管を利用し、しかもクリーニングとセットで効率よくサービスを受けてもらうことで、そのコストを最小限に抑える工夫をしています。
無駄な料金を取らず、サービスの中身で満足してもらいたいという姿勢が、「保管のみ不可」というルールの背景にあるのです。
こうした企業努力が、多くのリピーターを生んでいる理由にもなっています。
大型倉庫の維持費、温湿度管理コスト、在庫管理システムのコストなどにより利用料金が上がってしまう
保管サービスには見えないコストがたくさんかかっています。
たとえば、布団を適切に保管するためには広い大型倉庫が必要ですし、その倉庫を適温・適湿に保つための空調設備、その運用スタッフやシステムも必要になります。
これらのコストは、最終的にクリーニング料金に上乗せされることになるため、結果としてお客様が“望んでいない機能”にまでお金を支払う形になってしまいます。
しももとクリーニングでは、そうした不必要な価格上昇を避け、「本当に必要な部分にだけお金をかけてほしい」という思いから、保管サービスはあえて提供していません。
純粋なクリーニング品質にだけお金をかけてほしい
しももとクリーニングが一番大切にしているのは、「布団をきれいにすること」に全力を注ぐことです。
保管や付帯サービスにリソースを割くのではなく、洗浄、除菌、乾燥といったクリーニング工程にこそコストをかけ、お客様に“納得の仕上がり”を届けることを重視しています。
余計なサービスで料金が上がるよりも、「この価格でこのクオリティなら満足」と言ってもらえることを目指しているのです。
機能を増やすより、品質を磨く。
しももとクリーニングのぶれない姿勢がここに表れています。
理由5・家庭での保管を前提に、長期保存向けの清潔仕上げをしているから
リナビスでは、衣類やふとんをクリーニングする際に、長期保管にも耐えられるような「清潔仕上げ」を行っています。
たとえば、汚れや汗をしっかり落とすだけでなく、雑菌の繁殖を抑えるための処理や、カビやニオイの発生を防ぐような対応も丁寧に施されています。
そのため、自宅で保管することを前提としても、十分に安心できる状態で衣類や寝具を受け取れるのです。
わざわざ保管施設に預けなくても、自分のクローゼットや押し入れで大切に保管するだけで、次のシーズンまで気持ちよく使えるというのは、非常にありがたい配慮ですよね。
こうした仕上げの工夫があるからこそ、あえて「保管のみ」を提供しなくても、サービスとして成立しているのだと感じます。
家庭で安心して保管できるよう、中までしっかり乾燥・除菌して返してくれる
保管をお客様に任せるからには、「家庭での保管でも劣化しない仕上がり」であることが絶対条件になります。
しももとクリーニングでは、ふとんの中綿までしっかりと乾燥し、除菌処理を施した上で返却してくれるため、そのまま押し入れやクローゼットで保管しても安心です。
カビの原因となる湿気が残らないよう、高温の熱風で中まで乾かす工程を徹底しているのも特徴です。
これにより、長期間の保存中でも布団がふんわりとした質感を保ち、いざ使う時に「すぐ気持ちよく使える」状態で維持できるようになっています。
そのまま押し入れで長期保管しても問題ないクオリティに仕上げている
しももとクリーニングでは、「保管サービスをしない代わりに、保管できる品質で返す」ことをポリシーとしています。
家庭での長期保管を前提にしているからこそ、乾燥の精度や除菌力には徹底的にこだわり、湿気・菌・においの原因を徹底的に除去しています。
実際に、返却された布団をそのまま半年以上押し入れにしまっていても、ふっくら感や清潔さが損なわれなかったという声も多く寄せられています。
家庭での管理が前提とはいえ、そこに負担をかけないための“プロの仕上がり”があるからこそ、多くの方に支持されているのです。
しももとクリーニングに保管サービスのオプションはある?布団保管サービスのメリットとデメリットを解説
布団クリーニングのサービスを比較していると、「保管サービスつき」という言葉をよく目にしますよね。
特にオフシーズンの布団を預かってくれるというのは、一見とても便利に感じるものです。
ですが、しももとクリーニングではあえて保管サービスを提供していません。
それにはきちんとした理由があるのですが、まずは多くの人が保管サービスに魅力を感じる「メリット」から確認していきましょう。
しっかりメリットを知ることで、逆に「なぜそれを選ばないのか」の理由にも納得できるようになるはずです。
メリット1・自宅スペースが空く
保管サービスの一番のメリットは、自宅のスペースが確保できるという点にあります。
特に布団はかさばるため、クローゼットや押し入れの大部分を占めてしまいますよね。
夏用・冬用の入れ替えが必要なご家庭では、その保管場所をどうするかは毎年の悩みの種にもなりがちです。
そんな時に、クリーニングと一緒に預かってくれるサービスがあれば、物理的な収納の悩みが一気に解消されます。
空いたスペースには、季節のアイテムをゆったりと収納できるため、生活の中のゆとりにもつながるのが嬉しいポイントです。
メリット2・ふとんの管理をプロに任せられる
布団は自宅で管理するとなると、湿気や虫害、カビなど気を使うことが多いものです。
そんなときに保管サービスがあると、温度・湿度が管理された倉庫で専門のスタッフがしっかりと管理してくれるため、安心して任せることができます。
管理のプロが状態を見ながら保管してくれるというのは、忙しい方や体力に不安のある方にとってはとても心強いですよね。
「清潔な状態を保ったまま次に使える」という安心感は、まさにプロのサポートがあるからこそ得られる価値です。
自宅の環境に自信がないという方には、大きなメリットといえるでしょう。
メリット3・衣替えシーズンがラクになる
季節の変わり目になると、毎年のように押し入れを整理したり、布団を入れ替えたりと、けっこうな作業になりますよね。
保管サービスを利用していれば、こうした衣替えの時期の手間がぐっと減ります。
使わない布団をクリーニングに出して、そのまま次のシーズンまで預かってもらえることで、家庭内の作業量も物理的な負担も大幅に減るのです。
特に家族が多いご家庭では、布団の数も多くなるので、この手軽さは大きな魅力。
毎年の「面倒だな」というストレスがひとつ減るだけで、暮らし全体がずいぶんスムーズになります。
メリット4・次シーズンに合わせて配送指定できる
保管サービスでは、ただ預かるだけでなく「次のシーズンに合わせてお届け」してくれる便利な機能もあります。
これが意外と重宝するポイントなんです。
たとえば春に冬布団を預けておき、秋になったら指定した日にふっくら清潔な状態で戻ってくる……そんな風に、季節の始まりを快適に迎えられるのはとてもありがたいですよね。
予定が立てやすくなるだけでなく、「そろそろ使う時期かな?」と気にしなくて済むのも嬉しいところ。
生活リズムに合わせて布団が届く感覚は、忙しい現代人にぴったりの仕組みです。
メリット5・長期間使わない布団も最適な環境でキープできる
お客様用や季節外の布団など、長期間出番がない布団をどこでどう保管するかは意外と悩みどころです。
そんな時に、湿気や虫の心配がない環境でプロに管理してもらえる保管サービスは、とても心強い選択肢になります。
定期的に使用しない布団ほど、保管環境の差が品質に影響しやすいため、こうしたサービスのメリットは大きいのです。
「次に使うときも、気持ちよく眠りたい」という願いを叶えてくれるのが、最適な環境で保たれた清潔な布団。
それをプロに任せるという安心感は、家庭ではなかなか得がたい魅力かもしれません。
<
デメリット1・保管料金などの追加料金がかかる
保管サービスはとても便利ではありますが、その分どうしても追加料金がかかってしまうのが現実です。
クリーニング料金に加えて、保管日数や預ける点数によって費用が上乗せされることがほとんどで、トータルコストが想像以上に高くなってしまうこともあります。
特に家族分やシーズンごとに複数枚預けるとなると、保管料金が意外と大きな負担になるケースも少なくありません。
安さだけで選んでしまうと、オプションが重なった時に「結局高くついた」と感じてしまうことも。
こういった料金面の負担が、保管サービスを利用する上での最大のネックになりがちです。
デメリット2・保管中にふとんのふわふわ感が落ちるリスクがある
どれだけ設備が整った倉庫で保管されていても、長期間押しつぶされた状態で布団が保管されることによって、ふっくらとした質感が失われてしまうことがあります。
特に羽毛布団などは、空気をたっぷり含んでこそ快適な寝心地が得られるため、保管の方法によってはふわふわ感が落ちてしまうという声も。
これはクリーニング直後の最高のコンディションから少しずつ劣化していく、いわば“時間の経過によるマイナス”とも言えます。
使いたい時にボリュームがなくなっていたら残念ですよね。
そのリスクがある限り、しももとクリーニングではあえて保管しない姿勢を貫いているのです。
デメリット3・他人のふとんと同じ倉庫で保管されるリスクがある
保管サービスでは、どうしても他人の布団と同じ空間での保管になることが一般的です。
これは大規模な倉庫を効率的に使うために仕方のないことですが、いくらクリーニング済みとはいえ、人によっては「衛生面が気になる」「におい移りが心配」と感じることもあるでしょう。
とくに敏感肌の方やお子さまが使う布団の場合は、少しのにおいでも気になるもの。
他人の生活臭や洗剤の香りなどが布団に残ってしまうこともあり、「自分専用の布団」という感覚が薄れてしまうリスクもあります。
肌に触れるものだからこそ、こうした点は大切にしたいですよね。
デメリット4・預けたふとんをすぐ取り出せない場合がある
保管サービスを利用すると、自宅の押し入れには布団がなくなってスッキリしますが、逆に「必要な時にすぐ使えない」というデメリットも生まれます。
たとえば急な来客や季節外れの寒さが訪れた時に、「あの布団、今すぐ使いたい!」と思っても、すぐには手元に戻せないことが多いのです。
通常、保管倉庫から出荷されるまでに数日かかるため、緊急時の対応には向いていません。
「今すぐ欲しいけど間に合わない…」というストレスは、意外と大きなマイナス要素になる場合があります。
使いたい時にすぐ使える――そんな安心感がないのも、見逃せないデメリットのひとつです。
デメリット5・素材やサイズによっては保管できないものもある
布団にはさまざまな種類があり、中には特殊な素材や大きなサイズのものもあります。
そうした布団すべてが保管サービスに対応しているわけではないのが実情です。
たとえば、ムートン素材の敷布団や、キングサイズの大きな寝具、さらには敏感素材の特殊布団などは、倉庫の仕様上対応できないケースもあります。
預けたつもりが「対応不可で返却される」なんてことになると、かえって手間が増えてしまいますよね。
こうした受け入れ制限があることを知らずに申し込んでしまうと、トラブルの原因にもなりかねません。
安心して使うには、事前の確認が必須です。
しももとクリーニングに保管サービスはない?他の宅配クリーニングが行う布団保管方法を解説
しももとクリーニングでは保管サービスを行っていませんが、他の宅配クリーニング業者では布団の保管をオプションとして提供しているところが数多くあります。
では、その保管サービスはどのような環境・方法で行われているのでしょうか?ここでは、一般的な大手宅配クリーニング業者が行っている布団の保管方法についてご紹介します。
清潔な環境で預かってくれるのは魅力的ですが、実際には業者によって対応が異なる点も多く、事前に知っておくことで失敗やトラブルを避けられます。
しももとクリーニングの“あえて保管しない理由”を理解するためにも、比較対象としての他社の保管体制を知ることはとても大切です。
大手の宅配クリーニング業者はクリーニング工場内か、または近くに設置された専用保管倉庫に布団を預かります
大手の宅配クリーニング会社では、布団をクリーニングした後にそのまま預かる保管サービスを提供しているケースが多くあります。
保管場所としては、クリーニング工場の一部スペースを使う場合もあれば、工場とは別に設けた専用の保管倉庫に移動して管理することもあります。
こうした専用倉庫はセキュリティ面も強化されており、防犯カメラの設置や出入り管理などもきちんとされているところが多いようです。
ただし、どの業者も同じ保管環境とは限らず、設備や対応方針には差があるため、利用前に確認しておくことが安心につながります。
温度管理(だいたい20℃前後にキープ)、湿度管理(50%前後にキープ)の倉庫が多い
布団の保管環境で特に重視されるのが「温度」と「湿度」の管理です。
多くの業者では、倉庫内の温度を20℃前後、湿度を50%前後にキープすることで、カビやダニの発生を防いでいます。
空調設備を常時稼働させることで、外気の影響を最小限に抑え、ふとんが常に清潔で快適な状態を保てるよう努力されているのです。
ただし、これにはコストもかかるため、サービス料金に反映されていることもあります。
過剰な乾燥や湿度の変化によって素材が傷むリスクを考慮し、慎重に環境設定されているのが一般的です。
保管方法:圧縮するか、しないかは業者による
保管の際に布団を「圧縮するかどうか」は、業者によって対応が分かれるポイントです。
スペース効率を重視して圧縮保管を行う業者もあれば、布団のふくらみや質感を守るためにあえて圧縮しない方針をとっている業者もあります。
圧縮保管はスペースが節約できる反面、羽毛布団などではふっくら感が失われる可能性もあるため、デリケートな素材の場合には注意が必要です。
しっかりと元に戻す処理がなされているかどうかも業者によって異なりますので、希望する布団の種類によっては圧縮の有無も重要な選択基準となってきます。
布団同士は基本的に個別管理 or ラック保管
布団の保管方法については、どの業者も「他人の布団と直接触れさせない」ことを基本としています。
そのため、保管の際には1枚ずつ個別に包装し、それぞれを棚やラックに分けて保管するスタイルが一般的です。
多くの場合、専用の通気性カバーやビニール袋に包んだ状態で、棚番号やバーコードで管理されており、どの布団が誰のものかが明確に識別できるようになっています。
これにより、誤配送や紛失のリスクを減らしながら、においや雑菌の移りも防ぐことが可能になります。
また、通気性を確保しながらの保管ができるよう、ラックには空間が設けられており、布団同士が押し潰し合わないような工夫もされていることが多いです。
とはいえ、これらの方法にも完璧な隔離とは言い難い部分があるため、肌に直接触れる寝具においては、やはり気になる方も少なくありません。
そうした理由から、しももとクリーニングのように「そもそも保管しない」という姿勢を選ぶ事業者もあるのです。
ふとんごとに専用カバーやビニール包装をして保管してるケースが多い
布団の保管では、他の利用者の布団と触れ合わないよう、専用のカバーやビニール包装で個別に包む対応が一般的です。
中には通気性に配慮した不織布を使った包装を取り入れている業者もあり、湿気対策や型崩れ防止にも気を配っているところが多く見られます。
ふとん1点ずつが個別に管理されているため、預けた人の布団が識別されやすく、間違いが起きにくい体制が整っているのも安心材料のひとつです。
他人の布団と直接触れないため臭い移りのリスクが減る
保管中に気になるのが、他人の布団と触れ合うことで生じる“におい移り”のリスクです。
これを避けるために、多くの業者では個別包装やラック分けされた状態で布団を保管しています。
他の人の生活臭や柔軟剤の香りが移ることを防ぐための対策がとられているわけですね。
こうした対応によって、ある程度の衛生面や品質が保たれる仕組みにはなっていますが、それでも完全に個別の空間で保管されるわけではないため、しももとクリーニングのように“触れさせない前提”でサービスを設計している会社とは方針が異なると言えそうです。
しももとクリーニングに布団保管サービスはない?自宅で清潔に保管する正しい方法とは
しももとクリーニングでは保管サービスを行っていませんが、他の宅配クリーニング業者では布団の保管をオプションとして提供しているところが数多くあります。
では、その保管サービスはどのような環境・方法で行われているのでしょうか?ここでは、一般的な大手宅配クリーニング業者が行っている布団の保管方法についてご紹介します。
清潔な環境で預かってくれるのは魅力的ですが、実際には業者によって対応が異なる点も多く、事前に知っておくことで失敗やトラブルを避けられます。
しももとクリーニングの“あえて保管しない理由”を理解するためにも、比較対象としての他社の保管体制を知ることはとても大切です。
大手の宅配クリーニング業者はクリーニング工場内か、または近くに設置された専用保管倉庫に布団を預かります
大手の宅配クリーニング会社では、布団をクリーニングした後にそのまま預かる保管サービスを提供しているケースが多くあります。
保管場所としては、クリーニング工場の一部スペースを使う場合もあれば、工場とは別に設けた専用の保管倉庫に移動して管理することもあります。
こうした専用倉庫はセキュリティ面も強化されており、防犯カメラの設置や出入り管理などもきちんとされているところが多いようです。
ただし、どの業者も同じ保管環境とは限らず、設備や対応方針には差があるため、利用前に確認しておくことが安心につながります。
温度管理(だいたい20℃前後にキープ)、湿度管理(50%前後にキープ)の倉庫が多い
布団の保管環境で特に重視されるのが「温度」と「湿度」の管理です。
多くの業者では、倉庫内の温度を20℃前後、湿度を50%前後にキープすることで、カビやダニの発生を防いでいます。
空調設備を常時稼働させることで、外気の影響を最小限に抑え、ふとんが常に清潔で快適な状態を保てるよう努力されているのです。
ただし、これにはコストもかかるため、サービス料金に反映されていることもあります。
過剰な乾燥や湿度の変化によって素材が傷むリスクを考慮し、慎重に環境設定されているのが一般的です。
保管方法:圧縮するか、しないかは業者による
保管の際に布団を「圧縮するかどうか」は、業者によって対応が分かれるポイントです。
スペース効率を重視して圧縮保管を行う業者もあれば、布団のふくらみや質感を守るためにあえて圧縮しない方針をとっている業者もあります。
圧縮保管はスペースが節約できる反面、羽毛布団などではふっくら感が失われる可能性もあるため、デリケートな素材の場合には注意が必要です。
しっかりと元に戻す処理がなされているかどうかも業者によって異なりますので、希望する布団の種類によっては圧縮の有無も重要な選択基準となってきます。
布団同士は基本的に個別管理 or ラック保管
保管サービスを提供している宅配クリーニング業者の多くは、他人の布団と直接触れ合わないよう「個別管理」や「ラック保管」を基本としています。
布団はそれぞれ専用のビニール袋や通気性のある不織布カバーで包まれ、個別に識別番号やバーコードなどで管理される仕組みになっています。
これにより、誰の布団かをしっかり把握しつつ、異なるお客様の布団が混ざることを防いでいます。
また、大型のラックや棚を用いて1点ずつ間隔をあけて保管することで、圧縮や型崩れのリスクを抑えたり、空気の流れを確保する工夫がなされている場合もあります。
こうした管理体制は業者ごとに異なりますが、品質を意識している業者ほど、保管の丁寧さや清潔さに強くこだわっている傾向があります。
ただし、完全な隔離ではないため、におい移りや湿度管理の違いによる影響はゼロではなく、気になる方にとっては事前確認がとても大切です。
ふとんごとに専用カバーやビニール包装をして保管してるケースが多い
布団の保管では、他の利用者の布団と触れ合わないよう、専用のカバーやビニール包装で個別に包む対応が一般的です。
中には通気性に配慮した不織布を使った包装を取り入れている業者もあり、湿気対策や型崩れ防止にも気を配っているところが多く見られます。
ふとん1点ずつが個別に管理されているため、預けた人の布団が識別されやすく、間違いが起きにくい体制が整っているのも安心材料のひとつです。
他人の布団と直接触れないため臭い移りのリスクが減る
保管中に気になるのが、他人の布団と触れ合うことで生じる“におい移り”のリスクです。
これを避けるために、多くの業者では個別包装やラック分けされた状態で布団を保管しています。
他の人の生活臭や柔軟剤の香りが移ることを防ぐための対策がとられているわけですね。
こうした対応によって、ある程度の衛生面や品質が保たれる仕組みにはなっていますが、それでも完全に個別の空間で保管されるわけではないため、しももとクリーニングのように“触れさせない前提”でサービスを設計している会社とは方針が異なると言えそうです。
しももとクリーニングに布団保管サービスはない?自宅で清潔に保管する正しい方法とは
しももとクリーニングでは、布団の保管サービスはあえて行っていません。
しかしその理由は「仕上がったふとんを最高の状態で、自宅でしっかり管理してほしいから」という誠実な想いからきています。
とはいえ、自宅で布団をきちんと保管できるか不安な方もいらっしゃいますよね。
そんな方のために、ここでは“プロのクリーニング後の清潔な布団”を、家庭でもふんわり長持ちさせるための管理方法をわかりやすく解説します。
特別な道具も広いスペースも必要ありません。
ちょっとした工夫と、保管場所選びのコツを知っておくだけで、自宅でも布団を安心して保管できます。
これからお伝えする内容を参考にすれば、クリーニング後の仕上がりを保ちながら、次の季節も気持ちよく使うことができるはずです。
自宅管理の方法1・布団は必ず【完全に乾燥させて】から収納する
自宅で布団を保管する際にもっとも大切なポイントが、「完全に乾燥した状態で収納すること」です。
布団は湿気を含みやすく、そのまま収納してしまうと、カビやニオイの原因になってしまうことがあります。
とくに羽毛布団や綿布団は中綿が湿気を逃しにくいため、見た目が乾いていても内部にわずかな湿気が残っている場合があります。
これを放置すると、長期保管中に菌が繁殖しやすくなり、次に使うときに「においが気になる」「カビが…」なんてことも。
しももとクリーニングから返送された直後であっても、収納前には半日ほど陰干しを行い、軽く空気にさらしておくことがとても大切です。
これだけで、清潔で快適な状態を長くキープできます。
しももとクリーニング後、すぐ使わない場合でも返送されたふとんをいったん陰干しして
しももとクリーニングで丁寧に仕上げられた布団は、もちろん乾燥された状態で返ってきますが、輸送中に外気の影響でわずかに湿気がこもる可能性もあります。
そのため、届いた布団をすぐに使用しない場合は、いったん陰干しするのがおすすめです。
方法はとても簡単で、風通しの良い室内やベランダの日陰に布団を広げ、2~3時間ほど空気に触れさせるだけでOK。
直射日光に長時間当てると生地が傷むことがあるため、「陰干し」がポイントになります。
たったこれだけの手間で、布団の状態をより良く保つことができ、収納後のニオイや湿気トラブルを防げます。
クリーニングの仕上がりを最大限に活かすためにも、このひと手間はぜひ取り入れてくださいね。
軽く空気にさらして余分な湿気を飛ばすことでカビ・ニオイ防止効果がぐんとアップする
布団に残ったわずかな湿気やこもった空気は、放っておくとカビやニオイの原因になります。
特に押し入れやクローゼットの中は空気が滞りがちなので、収納前にきちんと空気にさらすことがとても重要です。
クリーニング後すぐであっても、軽く広げて風を通すだけで、余分な湿気を飛ばすことができ、その後の保管中のトラブルを大きく減らせます。
また、空気に触れることで布団がふんわりと膨らみ、圧縮によるシワや型崩れも回復しやすくなります。
こうした一手間は手間に思えるかもしれませんが、数か月後に再び使うとき、その違いをはっきりと実感できるはずです。
「ふわっとしてる」「気持ちいい」と感じる仕上がりを保つには、収納前のひと呼吸がとても大切です。
自宅管理の方法2・保管する場所は【湿気が少ない&風通しの良いところ】を選ぶ
布団の保管場所は、適当に押し込んでしまうと状態を悪くしてしまうことがあります。
特に気をつけたいのが「湿気」。
湿気の多い場所に長期間置いておくと、中綿にカビが生えたり、嫌なニオイが染みついたりしてしまいます。
ですから、保管場所には「通気性が良く、湿気がこもりにくい場所」を選ぶことがとても大切です。
押し入れやクローゼットを使う場合も、すのこや除湿剤を活用することで布団へのダメージを防ぐことができます。
また、壁にぴったりくっつけずに少し隙間を空けて収納することで空気が循環しやすくなり、湿気が逃げやすい環境を作ることができます。
ちょっとした工夫で、布団の清潔さとふわふわ感を長く保てるのです。
押し入れなら、上段のほうが風通しが良い
押し入れで布団を保管する場合、下段よりも上段のほうが湿気がこもりにくく風通しが良いため、保管には適しています。
とくに木造住宅や古い建物では、床に近いほど湿気が上がりやすく、結露などの影響も受けやすくなるため注意が必要です。
押し入れの上段を使う場合でも、すのこや布団用ラックを敷いて通気性を確保しておくと、さらに安心です。
また、定期的に押し入れの戸を開けて空気を入れ替えることも、カビ予防にはとても効果的です。
しっかり乾いた布団を、風が通る高い場所にふんわりとしまっておくことで、ふとんの状態をぐんと良く保てますよ。
クローゼットなら、壁から少し離して置くとカビが生えにくい
クローゼットに布団を収納する場合は、背面の壁から少しだけ離して置くのがポイントです。
壁にぴったりくっつけてしまうと、空気が流れず湿気がたまりやすくなり、カビの原因になってしまいます。
5センチ〜10センチほど隙間を作るだけで、通気性がグッと改善されます。
また、クローゼットの床には除湿シートや新聞紙を敷いて湿気対策をするとより安心です。
たまに扉を開けて換気してあげることで、内部の空気もリフレッシュできます。
布団は大切な寝具ですから、収納場所にもひと工夫して、ふわふわの状態をキープしてあげましょう。
湿気の多い床下収納や納戸は避けたほうが安心
床下収納や納戸など、空気の流れがほとんどない場所は、布団の保管場所としては避けたほうが安心です。
こうした場所は構造上どうしても湿気がこもりやすく、温度や湿度の変化も大きいため、布団の内部にカビや菌が発生するリスクが高まります。
収納スペースとして便利ではありますが、布団にとっては過酷な環境になりかねません。
高温多湿な夏場は特に注意が必要で、気づかないうちに布団に異変が…ということも。
安心して保管したいなら、やはり風通しが良く湿気が少ない場所を選ぶことが大切です。
少しの配慮で、大切な布団を長く清潔に使い続けることができますよ。
自宅管理の方法3・ 布団は【専用の通気性カバー】に入れて保管する
布団を長期間保管する際は、収納袋の選び方がとても重要です。
しっかり乾かした布団でも、密閉された環境ではわずかな湿気がこもってしまい、時間が経つとカビや嫌なニオイの原因になってしまいます。
そのため、通気性に優れた専用のカバーや不織布素材の布団袋に入れて保管するのが理想的です。
これらのカバーは、布団をほこりや汚れから守りつつ、湿気だけは外に逃がすような構造になっており、押し入れやクローゼットでも快適な保管環境をつくることができます。
また、最近では収納しやすいサイズや形状に工夫されたタイプも多く、立てて置ける布団ケースなども人気です。
大切な布団を守るために、袋選びにもぜひこだわってみてください。
不織布素材の布団袋や布製の通気性カバーを使おう
保管用の袋にはさまざまな種類がありますが、特におすすめなのが「不織布」素材の布団袋や、布製の通気性カバーです。
これらは布団の通気を妨げることなく、適度な湿気の調整が可能なため、長期保管にも向いています。
素材の構造が湿気を逃がしやすく、カビやニオイの原因になる水分を外に排出する効果があるため、湿度が高まりがちな押し入れでも安心して使用できます。
また、柔らかく扱いやすいため、布団を押し込む際に過剰な圧力をかけてしまう心配もありません。
最近では抗菌・防臭加工が施されたものもあり、より安心して保管したい方にはそちらもおすすめです。
選ぶ際は「通気性」と「扱いやすさ」を重視すると失敗がありません。
ビニール袋で密封保存(→内部に湿気こもる)は絶対にNG
見た目がきれいで扱いやすいからと、つい選んでしまいがちなのがビニール袋。
ですがこれは、布団保管においては絶対に避けたいNGアイテムです。
ビニールは空気も湿気も通さないため、一見すると衛生的に感じるかもしれませんが、実は布団内部に残ったごくわずかな湿気が外に逃げられず、袋の中にこもってしまいます。
これがカビやニオイの原因になり、せっかくクリーニングした布団が台無しになることもあるのです。
しかも湿度が高まったビニール内部は雑菌にとって理想的な環境。
そうならないためにも、必ず通気性のあるカバーや袋を選びましょう。
もしどうしてもビニールしかない場合は、一部に空気穴を開けるなどの工夫が必要です。
自宅管理の方法4・保管中も定期的に空気の入れ替えをする
布団を清潔に保ったまま長期間収納するためには、ただ“しまっておくだけ”ではなく、定期的に空気を入れ替えることがとても大切です。
たとえ完全に乾燥した状態でしまっても、季節の移り変わりや収納場所の環境変化によって、少しずつ湿気がたまり、布団が劣化する原因になることがあります。
そのため、1〜2ヶ月に一度のペースで収納から取り出し、軽く空気に触れさせるようにしましょう。
この習慣を取り入れるだけで、カビやニオイの発生リスクをかなり減らすことができます。
また、押し入れ自体の換気も同時に行うことで、収納環境そのものを整えることができます。
手間のように思えるかもしれませんが、布団を気持ちよく使い続けるためには必要な“お手入れ時間”です。
1〜2ヶ月に1回を目安にふとんを取り出して、軽く空気にさらそう
どんなに丁寧に収納しても、布団というのは空気の流れがないと湿気がこもりやすいものです。
そこでおすすめなのが、1〜2ヶ月に一度のペースで、布団を取り出して風通しの良い場所で軽く広げる習慣です。
中綿にこもった空気を入れ替えるだけでも、カビや雑菌の繁殖リスクを減らすことができます。
長期間出しっぱなしにする必要はなく、2〜3時間陰干しするだけでも効果があります。
カレンダーやスマホのリマインダーに「布団換気の日」として登録しておくのもおすすめです。
ほんの少しの手間で、布団の寿命がぐんと伸びて、次に使うときの“気持ちよさ”がまったく違ってきますよ。
晴れた日を選んで直射日光は避けた日陰干しで十分
布団を空気にさらす際に注意したいのが、「直射日光の当てすぎ」です。
確かに太陽の光は殺菌効果がありますが、長時間当ててしまうと布団の生地が劣化したり、色あせの原因になることがあります。
特にデリケートな素材や、羽毛布団・高級布団などは直射日光に弱いため、日陰での陰干しが最適です。
晴れた日の午前中や、風の通りが良い時間帯を選んで、風通しの良いベランダや室内に布団を広げておくだけで、湿気やこもった空気がしっかり抜けてくれます。
また、窓を開けて室内に干す場合は、エアコンの除湿モードやサーキュレーターを併用するとより効果的です。
日々のお手入れとして無理なく続けられる方法を選ぶことが、長く快適に使うための秘訣です。
自宅管理の方法5・防虫・防カビ対策も忘れずに
布団を自宅で清潔に保管するには、湿気やにおいだけでなく、「虫」と「カビ」に対する対策も欠かせません。
布団は天然素材を使っていることが多く、放っておくと虫に食われたり、湿気からカビが発生してしまうことがあります。
特に春から夏にかけては虫の活動が活発になる時期。
布団を何ヶ月も使わずに収納しておくと、その間に虫食いが起きてしまうことも。
そうならないためにも、防虫剤や除湿剤を使って、収納環境そのものを整えておくことがとても大切です。
しももとクリーニングで丁寧に仕上げられた布団だからこそ、保管環境にも気を配り、次に使うときに「やっぱり頼んでよかった」と感じられるような状態を保ちたいですね。
押し入れや収納スペースには市販の防虫剤&除湿剤を設置しよう
布団を収納する押し入れやクローゼットは、密閉されやすく湿気や虫がたまりやすい空間です。
そこでぜひ取り入れていただきたいのが、市販の「防虫剤」と「除湿剤」の設置です。
これらはホームセンターやドラッグストアでも簡単に手に入る便利なアイテムで、収納環境を衛生的に保つための心強い味方です。
除湿剤は湿気を吸収してカビの発生を防ぎ、防虫剤は虫の侵入や繁殖を防ぐ効果があります。
布団の近くにこれらを置くだけで、知らない間に発生する虫食いやカビを防げるため、非常に効果的です。
定期的に中身をチェックし、交換目安がきたら新しいものに取り替えることで、その効果をしっかり維持できます。
防虫剤は布団に直接触れない位置に置きましょう
防虫剤を使用する際には、その“置き場所”にも注意が必要です。
防虫剤は化学成分を含むものが多く、布団の生地や中綿に直接触れてしまうと、変色やにおい移りなどのトラブルにつながることがあります。
特に羽毛布団や天然素材の布団はデリケートなため、防虫剤が触れることで品質を損なう可能性もあるのです。
設置する際は、布団の上に置くのではなく、棚の端や収納スペースの隅、もしくは壁際など、直接触れない場所を選ぶのが安心です。
また、防虫剤には吊り下げ型や置き型などさまざまなタイプがありますので、収納スペースの形に合わせて選ぶと使いやすさもアップします。
安全に、そして効果的に使いましょう。
防虫剤には使用期限があります!期限切れになったら交換をしましょう
防虫剤は一度置けばずっと効果があるわけではなく、必ず“使用期限”があります。
一般的には3ヶ月〜半年程度で効果が薄れてしまうため、長期間そのままにしていると「虫対策をしていたつもりが、実は無防備だった」ということも…。
ですので、防虫剤はパッケージや本体に記載されている使用期限をしっかりチェックし、定期的に交換する習慣をつけましょう。
交換時期を忘れがちな方は、スマホのカレンダーやリマインダー機能に「防虫剤の交換日」を登録しておくのもおすすめです。
たったこれだけの習慣で、大切な布団を虫食いやニオイからしっかり守れます。
きれいにクリーニングされた布団を、次のシーズンも安心して使うための、大切なひと手間です。
しももとクリーニングは保管サービスなし!それでも利用を決めたユーザー実際の口コミを紹介します
布団クリーニングを検討するときに、多くの方が気になるのが「保管サービスがあるかどうか」ですよね。
最近では、クリーニングと保管がセットになった便利なサービスも増えていますが、しももとクリーニングはあえて「保管サービスなし」を選んでいます。
でも実際には、それを知った上で利用を決めた方々がたくさんいらっしゃるんです。
では、なぜ保管サービスがなくても選ばれているのか?ここでは、実際にしももとクリーニングを利用したユーザーさんのリアルな声を紹介していきます。
良い口コミ1・しももとは仕上がりが圧倒的だから、保管サービスがなくても全然満足でした
最初は正直、保管サービスがないと聞いてちょっと迷いました。
でも、実際にお願いしてみたら、布団の仕上がりが予想を遥かに超えていて…!触った瞬間からふわっとした感触と無臭の安心感で、「これはすぐ使いたい」と思うレベルでした。
保管どころか、すぐベッドに敷いて寝たくなるほどキレイに仕上がっていたので、逆に保管しなくてよかったかもと思ったくらいです。
良い口コミ2・保管してもらうより、キレイになった布団をすぐ使える方が嬉しかった
季節の変わり目に合わせて布団をクリーニングに出したのですが、届いた布団の状態があまりにも良くて、すぐに使いたくなってしまいました。
ふわふわで新品のような清潔感があって、保管して寝かせておくより、今すぐ使って寝たい!と思わせてくれる仕上がりだったんです。
しももとの丁寧な仕事ぶりが伝わってきて、「保管なしでも十分価値あるな」と納得できました。
良い口コミ3・通気性カバーを使ったり、除湿剤置いたら、家でも全然問題なかった
保管サービスがないと聞いたときは、「家で保管できるかな…」と少し不安でした。
でも、通気性のいいカバーに入れて、押し入れに除湿剤を置いたら、思った以上に快適に保管できたんです。
やってみると意外と簡単で、むしろ自分で管理できる安心感もありました。
ちょっとした工夫で十分きれいに保てると実感できた体験でした。
良い口コミ4・保管サービスが付くと料金上がるから、しももとはシンプルでいいと思った
価格重視で布団クリーニングを探していた私にとって、しももとのシンプルな料金体系はとてもありがたかったです。
保管サービス付きだと、便利な反面、どうしても料金が高くなってしまうのがネックでした。
その点、しももとは保管なしにすることでコストを抑えてくれていて、サービス内容も明瞭で安心でした。
必要な分だけ、という潔さも好印象でした。
良い口コミ5・保管なしのこともちゃんと説明してくれて、逆に信頼できた
サービス内容を見ていて「保管なし」というのが最初は気になっていました。
でも、サイトや問い合わせ対応でその理由を丁寧に説明してくれたことで、むしろその正直さに信頼感が持てたんです。
変に曖昧なオプションがあるより、しっかり割り切っていて分かりやすい。
しももとのポリシーを感じられて、安心して依頼できました。
悪い口コミ1・マンション暮らしだから、保管してもらえたらもっと助かったかな
うちは都内のマンションなので、収納スペースがとても限られていて…。
そのため、布団を保管する場所を確保するのがやっぱりちょっと大変でした。
保管付きだったらもっと楽だったかも…と思う瞬間は正直ありました。
特に家族分となると、収納のやりくりもひと苦労です。
それでもサービスの質は素晴らしかったので、次回は保管用スペースを先に準備しておこうかなと思います。
悪い口コミ2・押し入れの湿気が心配で、除湿剤たくさん使いました
布団の仕上がりには大満足だったんですが、自宅で保管する際の湿気対策に少し苦労しました。
特に梅雨の時期は押し入れの中が蒸しやすく、念には念を入れて除湿剤を多めに設置しました。
カビや臭いの心配があったので、ちょっと神経質になりすぎたかもしれませんが、それでもキレイな布団をキープしたいという思いから、手間は惜しみませんでした。
悪い口コミ3・せっかくキレイになったのに、忙しくてしまいっぱなしになりそうで怖かった
しももとでクリーニングしてもらった布団は本当にピカピカで大満足でした。
ただ、届いたタイミングと忙しさが重なって、すぐに出せずに押し入れにしまったままになるのが心配でした。
保管サービスがあれば、タイミングを見て取り出せたのにな〜という気持ちは少しありました。
でも、品質は本当に素晴らしかったので、次回は余裕のある時期に依頼したいなと思います。
悪い口コミ4・保管サービス付きなら、何も考えずにラクだったかな〜とは思った
正直に言うと、保管サービスが付いていたらもっと気軽にお願いできたのになという気持ちはあります。
収納スペースのこととか、除湿対策とか、そういう細かいことを考えなくていいという意味で、保管付きってやっぱり便利だなと。
でも、しももとの仕上がりにはすごく満足しているので、自分で工夫して保管する手間と引き換えにこのクオリティなら、納得感はあります。
悪い口コミ5・料金重視か、保管あり便利さ重視かでギリギリまで迷いました
クリーニングの依頼を決めるまで、料金を抑えるか、保管の便利さを取るかですごく迷いました。
結果的にしももとを選んだのは、他のユーザーさんの口コミで「仕上がりがいい」と知っていたから。
でも、保管付きの手間いらず感も捨てがたかったんです。
今は自宅での保管も工夫して乗り切れていますが、やっぱりどちらを優先するかは人によって違うなと感じました。
しももとクリーニングは保管サービスがある?についてよくある質問と回答
しももとクリーニングは「布団専門の宅配クリーニング」として多くの利用者に支持されていますが、利用前にはいくつか気になるポイントもありますよね。
たとえば「保管サービスはあるの?」「料金はどれくらい?」「毛布や大物も洗えるの?」といった疑問をお持ちの方も多いはずです。
ここでは、しももとクリーニングに関してよく寄せられる質問を取り上げて、わかりやすくお答えしています。
口コミや評判、料金体系、梱包の方法など、初めての方でも安心して利用できるように、実際の利用者の声や関連情報も交えて解説していきます。
しももとクリーニングの口コミや評判について教えてください
しももとクリーニングは、利用者からの満足度が高く、口コミでも高評価が多く見られます。
特に「仕上がりがふわふわ」「ニオイがしっかり取れている」といった声が目立ち、他社と比較しても品質面での信頼感があります。
また、自然派クリーニングにこだわっており、化学薬品を極力使わないやさしい仕上げが好評です。
スタッフの対応が丁寧で、問い合わせへの返信も迅速という声もあり、サービス全体への安心感が感じられます。
宅配型なので、重たい布団を持ち運ぶ必要がないのも大きな魅力です。
詳しい口コミや評価については、以下のリンクからチェックしてみてくださいね。
関連ページ:しももとクリーニングの口コミや特徴は?仕上がりや納期・料金について解説します
しももとクリーニングの利用料金について教えてください
しももとクリーニングでは、布団の枚数に応じた「パック料金制」を採用しており、非常にわかりやすい価格設定が特徴です。
1枚、2枚、3枚といったパックがあり、枚数が多いほど1枚あたりの料金がお得になる仕組みになっています。
また、布団の種類(羽毛布団、敷き布団など)やサイズによって一部追加料金がかかるケースもありますが、見積もり時点で明確に案内されるので安心です。
オプション料金や送料の条件も含めて、事前に全体の金額が把握できるのはうれしいポイントです。
費用感やお得なコースの詳細については、以下のページで詳しくご確認いただけます。
関連ページ:しももとクリーニングの料金は?宅配クリーニングのお得なコースや注意点について
しももとクリーニングの毛布の丸洗いはできる?
はい、しももとクリーニングでは布団だけでなく、毛布の丸洗いにも対応しています。
特に冬場に活躍する厚手の毛布や、お子さまが使うデリケートな素材の毛布も、丁寧な水洗いでふっくらと仕上げてくれます。
化学薬品を極力使わない自然派のクリーニング方法なので、肌が敏感な方やアレルギーをお持ちのご家族でも安心して利用できます。
また、毛布は布団よりもコンパクトに梱包しやすく、配送もスムーズです。
丸洗い後の仕上がりに驚かれる方も多く、「新品みたい!」との声も。
料金や取り扱いの注意点などは、以下のリンク先で詳しく紹介されていますので、ぜひ参考にしてみてください。
関連ページ:しももとクリーニングは毛布も丸洗いできる?おすすめポイントや宅配クリーニングの料金は?
しももとクリーニングの梱包方法について教えてください
しももとクリーニングでは、注文後に専用の集荷キットが自宅に届きます。
このキットには布団を詰める専用バッグと説明書が同封されており、初めての方でも手順に従うだけで簡単に準備ができます。
布団は無理に圧縮せず、ふんわりと畳んでバッグに入れるのが基本です。
キツく押し込んだり、ビニール袋で密封するのはNGですので注意しましょう。
また、配送時のトラブルを防ぐために、集荷伝票や注意事項も同封されています。
クリーニングする布団の種類や枚数によって梱包のコツが少し異なるため、事前に公式サイトやマニュアルを確認するのがおすすめです。
詳しい梱包手順については、以下のページで確認できます。
関連ページ:しももとクリーニングの布団の梱包方法や注意点/仕上がりまでの期間は?
しももとクリーニングの保管サービスについて教えてください
しももとクリーニングでは、現在のところ「布団の保管サービス」は提供していません。
これは品質に強いこだわりを持つ同社が、仕上がった布団をベストな状態で利用者に届けたいという方針によるものです。
保管中にふとんのふわふわ感が損なわれたり、湿気・ニオイが移るリスクがあることから、保管をあえて行わない選択をしています。
自宅での保管を前提として、しっかり乾燥・除菌された状態で返却されるため、安心してそのまま使うことができます。
なお、自宅保管のコツや注意点についても公式サイトや関連ページで詳しく紹介されていますので、合わせてチェックすると安心です。
関連ページ:しももとクリーニングには保管サービスはある?布団保管サービスのオプションや保管方法は?
しももとクリーニングのふとん丸洗いはドライクリーニングですか?
いいえ、しももとクリーニングのふとん丸洗いは「ドライクリーニング」ではなく、こだわりの「水洗い」です。
これは、汗や皮脂、ダニの死骸やハウスダストなど、水溶性の汚れをしっかり落とすための選択です。
ドライクリーニングは油性汚れに強い反面、水溶性の汗やニオイなどは落としにくいため、寝具にはあまり適していない場合があります。
しももとクリーニングでは、天然水を使い、中綿の奥までしっかりと洗い上げ、ふっくらとした仕上がりを追求しています。
肌に触れるものだからこそ、合成洗剤を極力使わない「やさしい水洗い」で、清潔かつ安心な眠りをサポートしてくれます。
しももとクリーニングは羽毛ふとんは洗えますか?
はい、しももとクリーニングでは羽毛布団も安心して預けることができます。
羽毛布団はデリケートな素材であるため、取り扱いに注意が必要ですが、しももとクリーニングでは専門知識をもったスタッフが一枚一枚丁寧に対応してくれます。
羽毛のボリュームを保ちながら、汚れや湿気をしっかりと落とすために、独自の水洗いと乾燥工程を採用しており、「仕上がりがふわふわ」と喜ぶ声も多数寄せられています。
また、乾燥も中までしっかり行われており、カビやにおいのリスクも極めて少ないです。
羽毛のつぶれや偏りを防ぐための丁寧な仕上げが特徴で、高価な羽毛布団も安心して預けられるのが魅力です。
しももとクリーニングは納期はどのくらいですか?
しももとクリーニングの納期は、通常でおおよそ10日〜14日程度が目安とされています。
ただし、繁忙期や布団の種類、オプションの有無によっては若干前後することもあります。
特に冬から春にかけての衣替えシーズンは注文が集中しやすいため、やや時間がかかる場合がありますが、その分丁寧に仕上げてくれるので安心です。
また、公式サイトでは最新の納期状況が随時更新されており、注文時にも目安の仕上がり日が確認できます。
急ぎの場合や特別な事情がある場合には、事前に問い合わせることで、可能な範囲で柔軟に対応してくれるケースもありますので、一度相談してみると良いでしょう。
しももとクリーニングのキャンセルについて教えてください
しももとクリーニングの注文をキャンセルしたい場合は、できるだけ早めにカスタマーサポートに連絡するのが基本です。
集荷キットの発送前であれば、無料でキャンセルできることがほとんどですが、キットが発送済み、または布団がすでにクリーニング工程に入っている場合は、キャンセルができない、もしくはキャンセル料が発生する場合もあります。
公式サイトの「よくある質問」や利用規約にはキャンセルの条件が明記されているため、事前にチェックしておくと安心です。
また、何か事情がある場合は、遠慮なく問い合わせてみると、丁寧に対応してくれるのもしももとクリーニングの魅力のひとつです。
しももとクリーニングの注文から仕上げまでの利用の流れについて教えてください
しももとクリーニングの利用の流れはとてもシンプルです。
まずは公式サイトから希望のコースを選んで注文を行うと、自宅に「集荷キット」が届きます。
このキットには、布団を入れる専用バッグや、送り状、説明書などが同封されています。
布団を説明通りにバッグに入れて、指定の配送業者に集荷を依頼するだけで、あとはしももとクリーニング側で丁寧に丸洗い・乾燥・仕上げを行ってくれます。
仕上がった布団はそのまま自宅に返送され、すぐに使える状態で届くのが特徴です。
自宅から一歩も出ずに完結するため、忙しい方や重い布団を運ぶのが難しい方にもピッタリのサービスです。
しももとクリーニングのダウンジャケットのクリーニング料金について教えてください
しももとクリーニングでは、ダウンジャケットのクリーニングにも対応しており、素材やブランドを問わず高品質な仕上がりが期待できます。
料金は、一般的なダウンであれば5,000円前後が目安となっており、モンクレールやカナダグースなど高級ブランド品の場合は、追加料金が発生することもあります。
これには、素材に応じた特別な洗浄や乾燥工程が含まれており、型崩れや風合いの変化を防ぐための丁寧な作業が行われます。
また、料金には送料や補修などのサービスも含まれていることが多く、コストパフォーマンスの面でも納得できる価格設定になっています。
事前に見積もりを確認することで、より安心して依頼できます。
しももとクリーニングのペット用品の宅配クリーニングサービスはどのようなものですか?
しももとクリーニングでは、ペット用のベッドやマット、ブランケットなどの宅配クリーニングにも対応しています。
ペット用品は毛や臭いが染みつきやすく、自宅で洗うには限界があるもの。
そんなときにこのサービスを利用すれば、専用の洗剤と機器を使って、奥までしっかり洗浄・除菌してもらえます。
特にアレルギーや敏感肌のペットにも配慮し、なるべく化学薬品を使わない優しい洗い方が特徴です。
人間用と分けて洗ってくれるので、衛生面も安心。
ペットが快適に過ごせる清潔な環境を保ちたい方にぴったりのサービスです
参照:よくある質問(しももとクリーニング)
しももとクリーニングに布団保管サービスはある?人気の宅配クリーニングと徹底比較
宅配クリーニングを選ぶとき、「保管サービスがあるかどうか」は意外と大きな判断材料になりますよね。
とくにオフシーズンの布団やかさばる寝具などは、自宅で保管するスペースが限られているご家庭も多く、「預かってもらえたら助かるのに…」と感じる方も多いはずです。
しかし、しももとクリーニングでは、あえて保管サービスを提供していないという独自のスタンスをとっています。
それにはしっかりとした理由があり、ただ“ない”というよりも“あえて提供しない”という考え方なのです。
そこで今回は、しももとクリーニングの保管対応について、保管サービスを行っている他の宅配クリーニング業者と比較しながら、その違いと魅力をやさしく解説していきます。
サービス選びで迷っている方にとって、きっと納得の材料になるはずです。
| サービス名 | 対応地域 | クリーニング内容 | 料金 |
| リナビス | 全国 | 衣類、スーツ、着物、毛皮、布団、皮革、ブランド品、バッグ、靴、カーテン、絨毯、テントなど | ・衣類3点コース7,800円~
・着物コース14,300円 ・毛皮コース22,600円 ・布団1枚10,500円 など |
| しももとクリーニング | 全国 | 布団 | ・羽毛毛布1枚11,880円 |
| Loop Laundry | 全国 | 衣類、寝具、カーテンなど | ・9,700円/月
※サブスクサービスです |
| 宅配クリーニング 大和屋 | 全国 | 衣類、布団 | ・掛け布団1枚14,450円 |
| GiVu | 全国 | 衣類、布団、バッグなど | ・クリーニングバック6,500円~ |
| カジタク | 全国 | 衣類、布団など | ・布団1枚13,640円~ |
| リネット | 全国 | 衣類、靴、布団など | ・ダウンジャケット1枚2,970円~ |
| せんたく便 | 全国 | 衣類、布団、ぬいぐるみ、靴、革など | ・ダウンジャケット1枚1,053円~ |
| モクリン | 全国 | 衣類 | ・3点コース10,780円 |
| プラスキューブ | 全国 | 衣類 | ・5点パック11,000円 |
| フラットクリーニング | 全国 | 衣類 | ・10点パック9,339円 |
| クリーニングモンスター | 全国 | 衣類、布団、ぬいぐるみ | ・5点コース13,200円 |
しももとクリーニングに保管サービスはある?布団保管の有無や自宅での正しい保管方法まとめ
「しももとクリーニングって保管サービスあるのかな?」と気になっている方は多いかもしれません。
最近では、宅配クリーニングとセットで保管サービスを提供する業者も増えてきており、使わない布団を預かってくれるのは便利なサービスに思えますよね。
しかし、しももとクリーニングではあえてその保管サービスを行っていないのが実情です。
ただ、それは“サービスが足りないから”ではなく、“品質を何よりも大切にしているから”という理由があるんです。
このページでは、しももとクリーニングの保管対応の有無をはっきりさせつつ、なぜ保管を行わない方針なのか、その裏にある考えやこだわり、また家庭でできる保管方法のポイントまでを丁寧にまとめていきます。
布団を安心して預けたい方も、自宅での保管に不安がある方も、ぜひ参考にしてみてくださいね。