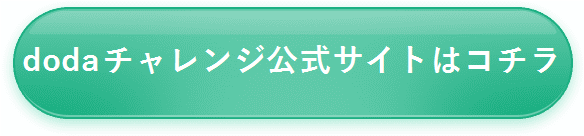dodaチャレンジで断られた!?断られる人の特徴や断られた理由について解説します

dodaチャレンジは、障がい者向けの転職支援サービスとして多くの求職者をサポートしていますが、中には「登録したのに紹介を断られてしまった」「希望する求人を紹介してもらえなかった」というケースもあります。
なぜdodaチャレンジで求人を紹介してもらえないことがあるのか?断られる理由や特徴について詳しく解説します。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジに登録したものの、キャリアアドバイザーから「紹介できる求人がない」と言われてしまうことがあります。
その理由の多くは、希望条件が厳しすぎるために、該当する求人がないケースです。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
例えば、「在宅勤務のみ」「フルフレックス勤務」「年収500万円以上」など、条件が非常に限定的だと、該当する求人の数が極端に少なくなります。
特に、障がい者雇用枠での在宅勤務の求人は、一般の転職市場に比べてまだまだ少なく、企業側も「出社できる人材」を優先する傾向があります。
そのため、フルリモートにこだわると、求人の選択肢がかなり限られてしまう可能性があります。
また、年収500万円以上の求人を希望する場合も、企業側が求めるスキルや経験がかなり高く設定されるため、該当する求人が少なくなりがちです。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
デザイナー、イラストレーター、アーティストなどのクリエイティブ職や、研究職、コンサルタントなどの専門職は、求人数がもともと少ないため、マッチする求人を見つけるのが難しくなります。
また、企業側も専門的なスキルや実務経験を重視するため、未経験での転職を希望する場合は、難易度が高くなることがあります。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
地方に住んでいる場合、その地域での障がい者雇用の求人が少ないことが理由で、紹介が難しくなるケースがあります。
大都市圏(東京・大阪・名古屋など)では障がい者向けの求人が比較的多いですが、地方ではそもそも求人数が少なく、希望する条件に合う企業が見つかりにくいことがあります。
この場合、勤務地を広げて検討したり、在宅勤務可能な求人を探すことで選択肢を増やすことができます。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジでは、すべての求職者に対して求人紹介を保証しているわけではなく、一部のケースではサポート対象外と判断されることがあります。
障がい者手帳を持っていない場合(「障がい者雇用枠」での求人紹介は、原則手帳が必要)
dodaチャレンジの求人の多くは「障がい者雇用枠」のため、原則として障がい者手帳を持っていることが条件となります。
手帳を持っていない場合、応募できる求人が極端に少なくなるため、キャリアアドバイザーから「紹介できる求人がない」と言われてしまうことがあります。
ただし、企業によっては、医師の診断書や通院履歴があれば選考を受けられる場合もあるため、手帳がない場合でも一度相談してみると良いでしょう。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
過去に一度も正社員やアルバイトなどの職務経験がない場合や、長期間(数年以上)働いていない場合、企業側が採用に慎重になることがあります。
これは、ブランクが長いと「職場復帰できるかどうか不安」「仕事のリズムに慣れるまで時間がかかるかもしれない」といった懸念を持たれやすいためです。
この場合は、就労移行支援や短時間勤務の求人からスタートすることで、少しずつ職務経験を積み、再就職のチャンスを広げるのが良い方法です。
体調が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
dodaチャレンジでは、求職者が安定して働ける環境を重視しており、体調が不安定な場合はすぐに求人を紹介するのが難しいことがあります。
特に、長期間のブランクがあったり、現在も頻繁に通院している場合は、「まずは生活リズムを整えてからの就職が望ましい」と判断されることもあります。
そのため、面談時に「現時点でフルタイム勤務が難しい」「体調が安定せず、長時間働ける自信がない」と伝えた場合、就労移行支援や障がい者向けのトレーニングプログラムを紹介されるケースもあります。
就労移行支援を利用することで、働くためのスキルを身につけたり、短時間勤務から徐々に慣れていくことができるため、焦らずに準備を進めることが大切です。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
dodaチャレンジの面談は、求職者の希望や適性をキャリアアドバイザーが判断する大切な機会です。
しかし、面談での受け答えが不十分だったり、準備不足が目立つ場合、求人の紹介が難しくなることがあります。
以下のようなケースでは、企業へのマッチングが難しいと判断される可能性があります。
障がい内容や配慮事項が説明できない
面談では、「どのような配慮が必要か?」を詳しくヒアリングされます。
しかし、自分の障がい特性や職場での配慮事項を明確に説明できないと、キャリアアドバイザーも適切な求人を提案することが難しくなります。
例えば、「長時間のデスクワークが厳しい」「週に1回通院が必要」「ストレスの少ない環境が望ましい」など、自分の働き方に必要な条件を整理しておくことが大切です。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
「とにかくどこでもいいから働きたい」「自分に向いている仕事がわからない」といった曖昧な回答をしてしまうと、キャリアアドバイザーも求人を絞り込むことが難しくなります。
具体的な職種や業界が決まっていなくても、「接客よりは事務職がいい」「できればチームで働く環境がいい」など、大まかな方向性を伝えられるように準備しておきましょう。
職務経歴がうまく伝わらない
過去の職歴を簡単に説明できない場合も、求人紹介がスムーズに進まないことがあります。
特に、転職回数が多かったり、ブランクがある場合は、その理由を明確に説明できるようにしておくとよいでしょう。
例えば、「前職では○○の業務を担当し、△△のスキルを身につけた」「ブランクの間に資格取得の勉強をしていた」など、職歴のポイントを整理しておくと、スムーズに伝えられます。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
dodaチャレンジは全国対応のサービスですが、地域によっては求人の数に差があります。
特に、都市部に比べて地方では求人が少ないため、希望の条件に合う仕事が見つかりにくいことがあります。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
首都圏や大阪・名古屋などの都市部では、障がい者雇用枠の求人が豊富にありますが、地方では企業の数自体が少ないため、求人数も限られています。
そのため、「地元で働きたい」と希望しても、マッチする求人がなかなか見つからないケースがあります。
この場合、選択肢を広げるために「近隣の都市まで通勤可能かどうか」「在宅勤務も視野に入れるか」など、条件を少し調整することも検討してみるとよいでしょう。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
最近では在宅勤務が可能な求人も増えていますが、障がい者雇用枠では「出社が基本」となる企業が多いため、完全在宅勤務のみを希望すると、求人が非常に限られてしまうことがあります。
特に、地方在住の方が「完全在宅勤務でしか働けない」となると、選べる求人が極端に少なくなり、紹介が難しくなるケースがあります。
この場合、週に数回の出社が可能かどうかを検討したり、オンラインでの業務が可能な企業を探すなど、柔軟に対応することが大切です。
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった場合、その理由はさまざまですが、多くは「希望条件が厳しすぎる」「準備不足」「求人数の少ないエリアに住んでいる」などが関係しています。
もし「求人を紹介してもらえなかった」と感じた場合は、キャリアアドバイザーと相談しながら希望条件を見直したり、他の転職エージェントと併用してより多くの選択肢を探すことをおすすめします。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
dodaチャレンジに登録する際、入力した情報が正確でない場合や、意図的に事実と異なる内容を記載した場合、サポートを受けられなくなる可能性があります。
登録情報は、キャリアアドバイザーが求人を紹介する際の重要な判断材料となるため、正確な情報を記載することが大切です。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
dodaチャレンジの求人の多くは「障がい者雇用枠」のため、基本的には障がい者手帳の取得が前提となります。
そのため、手帳を持っていないのに「取得済み」と誤って登録してしまうと、後から求人への応募ができなくなることがあります。
手帳の取得を検討している段階であれば、その旨を正直に記載し、アドバイザーに相談するのがよいでしょう。
一部の企業では、診断書や通院歴があれば応募可能な場合もありますので、まずは自身の状況を正しく伝えることが大切です。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
求職者の中には、「とりあえず登録しておこう」と考えてdodaチャレンジに申し込む方もいます。
しかし、実際に働ける状況ではない場合、求人を紹介してもらうことが難しくなります。
特に、健康状態が安定していなかったり、長時間の勤務が難しい場合は、まずは医師や専門家と相談し、就労が可能な状態かどうかを確認することが重要です。
dodaチャレンジでは、就職活動が厳しいと判断された場合、就労移行支援の利用を勧められることもあります。
職歴や経歴に偽りがある場合
登録時に職歴や経歴を偽って記載すると、企業との面接時に不整合が発覚し、不採用となるケースがあります。
また、キャリアアドバイザーが最適な求人を紹介するためには、正確な情報が必要です。
例えば、「過去にIT企業でエンジニアとして働いていた」と記載したものの、実際にはIT未経験だった場合、企業の求めるスキルレベルと合わず、結果的に選考が進まないことになります。
自分のスキルや職歴は正直に記載し、実力に合った求人を探すことが大切です。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
dodaチャレンジに登録できても、応募した企業から不採用の通知を受けることは珍しくありません。
しかし、この場合はdodaチャレンジが求職者を断っているわけではなく、あくまで企業の採用基準による判断です。
不採用は企業の選考基準によるもの
企業が求職者を不採用とする理由はさまざまですが、一般的には以下のようなケースが考えられます。
1. 求めるスキルや経験が不足している
企業が募集しているポジションに対して、求職者のスキルや経験が不足している場合、不採用になることがあります。
特に専門職の場合、実務経験が必須とされることが多いです。
2. 他の候補者との比較による結果
企業は複数の応募者を比較しながら選考を進めます。
そのため、最終的に他の候補者がより適任と判断された場合、選考に通らないことがあります。
3. 障がいの配慮が難しいと判断された
企業によっては、障がい者雇用の受け入れ態勢が十分に整っていない場合があります。
そのため、職場での配慮が難しいと判断された場合、不採用になることもあります。
dodaチャレンジを利用していても、すべての応募先から内定をもらえるわけではありません。
不採用になった場合は、キャリアアドバイザーに相談しながら、応募書類の改善や別の求人への応募を検討することが大切です。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか体験談や口コミを調査しました
dodaチャレンジは、多くの障がい者の方が転職を成功させている一方で、「登録したけれど、求人を紹介してもらえなかった」「希望する仕事が見つからなかった」という声もあります。
では、実際にどのような理由で求人を紹介されなかったのでしょうか? ここでは、dodaチャレンジで求人を紹介されなかった方々の体験談を紹介します。
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。紹介できる求人がないと言われてしまいました
この方のように、職歴が軽作業に偏っていたり、PCスキルが限られている場合は、事務系や専門職への紹介が難しいと判断されることがあります。
dodaチャレンジの求人は、一定のスキルを前提としていることも多いためです。ただし、だからといって可能性が閉ざされるわけではありません。
職業訓練でWordやExcelを学んだり、簡単な資格を取得することで求人の幅は広がります。求人がなかったのは「今の自分に合う仕事が少なかった」だけであり、スキルを積むことで未来の可能性はぐっと広がるんです。
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
このケースでは、働き続ける体力や生活リズムが整っていないことが理由で、すぐに求人紹介へ進めなかったようです。
企業としても「継続して勤務できるかどうか」を重視するため、dodaチャレンジも慎重にならざるを得ないのです。
ただし、就労移行支援を経ることは「遠回り」ではなく「準備期間」です。
支援事業所での通所や訓練を通じて生活リズムを整え、自分に合った働き方を模索することで、将来的に安定した就労へとつながります。断られたのではなく「今は準備の時期」と前向きにとらえたいですね。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。dodaチャレンジに相談したものの、『ブランクが長く、就労経験が直近にないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう』と提案されました
長期のブランクがある方にとって、再就職は大きな不安要素ですよね。
この体験談の方も、10年以上の療養期間があったため、まずは体調の安定を優先するよう提案されたのです。
企業にとっては「直近での就労経験」が重視されることが多いため、ブランクが長いと選考のハードルが高くなってしまうのは事実です。
ただし、それは「働けない」という意味ではなく、「準備が必要」というだけ。職業訓練や就労移行支援を活用し、少しずつ自信を取り戻していけば、また新しいスタートを切ることは十分可能なんです。
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
地方に住んでいる方にとって、求人の少なさはどうしても避けられない課題です。この方は在宅でのクリエイティブ職を希望していましたが、dodaチャレンジが保有する求人の中では該当する案件がなかったのでしょう。
在宅ワークやデザイン系の求人は都市部中心であることが多く、地方在住だと紹介が難しくなるケースが目立ちます。
ただ、クラウドソーシングを活用して実績を積んだり、在宅ワークに強い別のエージェントを利用するなど、工夫できる選択肢はあります。諦めずに複数の方法を試すことが大切です。
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。dodaチャレンジに登録したら、『現時点では正社員求人の紹介は難しいです』と言われました
アルバイトや派遣での経験が中心の場合、正社員を前提とした求人に応募するのは難しいことがあります。
企業側は「長く働けるかどうか」「責任のある業務を任せられるか」を重視するため、正社員経験がないとマッチングが難しくなるのです。
ただし、これは一生正社員になれないという意味ではありません。
契約社員や紹介予定派遣からスタートして実績を積む方法もあります。小さな一歩を重ねることで、将来的には正社員を目指せる道が開けていくのです。最初から完璧を求めず、段階的に進む姿勢が大切です。
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
このケースでは、希望条件が非常に限定的であったため、紹介可能な求人が見つからなかったようです。
「完全在宅・時短・高収入・事務職」というすべての条件を同時に満たす求人は、現実にはほとんど存在しません。
ただし、条件の一部を柔軟に見直すことで、新しい可能性が開けます。たとえば「完全在宅ではなく週1出社可」「時短勤務優先で年収は応相談」といった調整をすれば、選択肢は増えていきます。
子育てとの両立は大きな課題ですが、段階的に働き方を整えることで、少しずつ理想に近づけるはずです。
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
dodaチャレンジは障がい者雇用枠を前提としたサービスのため、障がい者手帳がないと登録や求人紹介が難しいケースがあります。
この体験談の方のように診断を受けていても、手帳がないと制度上の枠に当てはまらないのです。ただし、手帳の申請は主治医や自治体に相談すれば進められる場合が多く、取得後に改めて登録することでサービスを利用できるようになります。
手帳取得までの間は、ハローワークや一般枠での就職活動を併用するのも一つの方法です。
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
在宅でのITエンジニア職は人気が高く、企業も即戦力を求めることが多いため、未経験からの挑戦はハードルが高いのが現実です。
この方のように希望とスキルが一致しない場合は、紹介を受けるのが難しくなります。ただし、諦める必要はありません。独学やスクールでプログラミングを学び、ポートフォリオを作成することで将来的な可能性は広がります。
最初はデータ入力や簡単な在宅ワークから始め、少しずつ実績を積みながらIT職に近づいていく方法もあります。
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
身体障がいで通勤が難しい場合、在宅勤務の求人は大きな希望となりますが、まだ求人数が限られているのが現状です。
特に「短時間勤務の在宅ワーク」となると、さらに選択肢は少なくなります。この方のように紹介が受けられなかった場合でも、クラウドソーシングを活用して在宅の仕事を始めるなど、自力で実績を積む道もあります。
その実績をもとに、再度dodaチャレンジや他のエージェントに相談すれば、可能性は広がっていくかもしれません。
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。
この方は、障がい者雇用枠で「管理職」や「高収入」を希望したため、該当する求人がなく紹介を受けられなかったケースです。
障がい者雇用は、一般的に事務補助やオペレーション業務などが中心であり、管理職や高収入ポジションは非常に少ないのが現実です。
ただし、実績やスキルによっては将来的に昇進や給与アップが可能な企業もあります。最初から理想条件をすべて満たすのは難しくても、段階的にキャリアアップを目指す道を考えることが現実的な戦略です。
dodaチャレンジで断られたときの詳しい対処法について紹介します
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった場合、スキルアップや他の転職サービスの活用など、適切な対策を取ることで転職成功の可能性を高めることができます。
ここでは、dodaチャレンジで断られた理由別に、具体的な対処法を紹介します。
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
スキルや職歴が不足している場合、まずは職業訓練や資格取得を活用し、スキルアップを図ることが重要です。
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
ハローワークでは、求職者向けに無料または低額で受講できる職業訓練を提供しており、事務職を目指す場合はWord・Excelのスキルを習得することで、応募できる求人の幅が広がります。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
就労移行支援を利用すると、実際の職場を想定した業務トレーニングや、メンタル面のサポートを受けながら働く準備ができるため、安定した就職につながりやすくなります。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
資格を取得することで、スキルを証明でき、企業側も採用を検討しやすくなります。
特に、事務職を希望する場合は、MOSや日商簿記3級を取得すると、応募できる求人が増える可能性があります。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養期間があるなど)の対処法について
ブランクが長い場合、段階的に復職を目指す方法を検討することが大切です。
– 短時間のアルバイトやパートから始める
– 就労移行支援で職業訓練を受ける
– リワークプログラムを活用して、働くリズムを取り戻す
また、ブランク期間中に取り組んだこと(資格取得、ボランティア活動など)を履歴書に記載することで、企業に前向きな姿勢をアピールできます。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
就労移行支援は、働くためのスキルを学びながら、生活リズムを整えるのに適したサービスです。
毎日通所することで、働く習慣が身につき、面接時にも「継続して就労できること」をアピールしやすくなります。
また、職場実習を通じて企業と接点を持ち、採用につながるケースもあります。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
いきなりフルタイムでの勤務が難しい場合、まずは短時間のアルバイトや在宅ワークから始めるのも有効です。
週に1〜2回から働き始め、徐々に勤務日数を増やすことで、企業側に「安定して働ける」という実績を示すことができます。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
就労移行支援の一環として行われる企業実習や、ハローワークのトライアル雇用を活用すると、実務経験を積むことができます。
特に、企業実習を経験しておくと、dodaチャレンジに再登録する際に「実務経験あり」として評価されやすくなります。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
dodaチャレンジは全国対応ですが、地域によっては求人数が少なく、特に地方では選択肢が限られることがあります。
フルリモートの求人を希望する場合は、他の転職サービスやフリーランスの仕事も検討するのがおすすめです。
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
dodaチャレンジ以外にも、在宅勤務の求人を扱う障がい者専門のエージェントがあります。
atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレなどのサービスを併用することで、より多くの求人に出会う可能性が高まります。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
在宅で働く経験を積みたい場合、クラウドソーシングを利用するのも一つの方法です。
ランサーズやクラウドワークスでは、ライティングやデータ入力の仕事が多く、未経験でも始めやすい案件があります。
実績を積むことで、企業のリモートワーク求人に応募する際のアピール材料にもなります。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地方に住んでいる場合は、地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談すると、地元の企業が募集している求人を紹介してもらえることがあります。
特に、障がい者雇用枠の求人は、一般の求人サイトには掲載されていないこともあるため、地元の支援機関を活用するのがおすすめです。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
求人を紹介してもらえなかった理由として、希望条件が厳しすぎるケースもあります。
企業側の採用条件と求職者の希望が合わないと、紹介できる求人が見つからないことがあります。
このような場合、条件を柔軟に見直すことで、求人の選択肢が広がります。
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
転職活動を進める際に、すべての条件を満たす求人を探そうとすると、選択肢が狭まり、結果的に良い求人に出会えなくなることがあります。
そのため、「絶対に譲れない条件」と「できれば希望する条件」を分けて考えることが重要です。
例えば、「完全在宅勤務」「週3勤務」「年収○万円以上」などの希望がある場合、本当に譲れない条件なのかを整理することが大切です。
在宅勤務を希望する場合でも、週1〜2回の出社が可能であれば選択肢が広がるかもしれません。
また、週3勤務にこだわらず、最初は週4日勤務で様子を見るなど、柔軟に考えることで、より多くの求人に出会える可能性があります。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
dodaチャレンジのキャリアアドバイザーに相談する際、最初に提示した希望条件で求人が見つからなかった場合は、一部の条件を見直して再相談するのも一つの方法です。
例えば、勤務時間や出社頻度を少し緩和することで、マッチする求人が増える可能性があります。
完全在宅勤務にこだわらず、リモートワークと出社の併用を検討すると、より多くの企業の選考対象になります。
また、勤務地の範囲を広げることで、通勤可能なエリアの求人が増え、希望に近い仕事を見つけやすくなります。
こうした条件の調整をアドバイザーと相談しながら進めることで、自分に合った求人を紹介してもらいやすくなります。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
希望する条件をすべて満たす求人を探すのが難しい場合、まずは条件を緩めてスタートし、段階的にキャリアアップを目指す方法もあります。
最初から理想の働き方を実現するのは難しいことも多いため、まずは経験を積むことを優先し、スキルアップしながら理想の働き方に近づける戦略を立てると良いでしょう。
例えば、希望する年収に届かない場合でも、まずは現実的な年収の求人で経験を積み、数年後に転職や昇進を目指すこともできます。
また、最初は短時間勤務や契約社員として働き、スキルを身につけた後に正社員登用を目指すのも一つの方法です。
長期的なキャリアプランを考えながら柔軟に対応することで、最終的に希望に近い働き方を実現しやすくなります。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
dodaチャレンジの障がい者雇用枠の求人は、基本的に障がい者手帳を持っていることが条件となっています。
そのため、手帳を取得していない場合や、取得の手続きが進んでいない場合は、別の方法を検討する必要があります。
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
精神障がいや発達障がいのある人の中には、手帳を取得できることを知らなかったり、手続きが複雑に感じて申請をしていない人もいます。
しかし、手帳があることで応募できる求人の幅が広がるため、まずは主治医や自治体の福祉窓口に相談し、取得の可能性を確認することが重要です。
精神障がい者保健福祉手帳の場合、診断書の内容や病歴によって取得できることがあるため、医師とよく相談しながら進めることが大切です。
また、手帳を取得することで、就職後に受けられる支援や合理的配慮が増えることもあるため、長期的に見てメリットが大きいと言えます。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳を取得しないまま転職活動を進めたい場合は、一般枠での就職活動を検討するのも一つの方法です。
ハローワークや就労移行支援では、手帳がなくても応募できる求人を紹介してくれることがあります。
また、就労移行支援を利用して実績を積み、その後手帳を取得してからdodaチャレンジに再登録する方法もあります。
就労移行支援では、ビジネスマナーやPCスキルのトレーニングを受けながら、安定した職場への就職を目指すことができます。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
障がい者雇用枠での転職活動が難しい場合、まず体調管理や治療を優先し、安定した状態になってから手帳を取得し、再度転職活動を進めるのも一つの方法です。
手帳の取得には一定の診断期間や手続きが必要ですが、取得後は障がい者枠の求人に応募しやすくなるため、長期的に見て転職の選択肢を増やすことができます。
焦らずに自分のペースで準備を進めることが大切です。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった場合でも、他の転職サービスや支援機関を活用することで、新たなチャンスを見つけることができます。
例えば、障がい者向け転職エージェント(atGP、サーナ、アットジーピーなど)を活用すると、より多くの求人を紹介してもらえる可能性があります。
また、ハローワークや地域の就労支援機関に相談することで、地元の求人情報を得ることができるかもしれません。
複数の転職サービスを併用しながら、自分に合った働き方を探していくことが大切です。
dodaチャレンジで断られた!?発達障害や精神障害だと紹介は難しいのかについて解説します
dodaチャレンジは障がい者向けの転職支援サービスとして、多くの企業の求人を取り扱っています。
しかし、障がいの種類によっては、求人紹介が難しく感じるケースもあります。
特に、精神障害や発達障害のある方が「dodaチャレンジでは求人を紹介してもらえなかった」と感じることがあるようです。
このような状況が起こる背景には、企業側の受け入れ体制や合理的配慮の難しさが関係しています。
本記事では、身体障害、精神障害、発達障害を持つ方の就職事情について詳しく解説し、dodaチャレンジでの紹介が難しい場合の対策についても紹介します。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障害者手帳を持つ方は、比較的求人が多く、就職しやすい傾向にあります。
これは、身体的な障がいは企業側にとって「合理的配慮を行いやすい」という特徴があるためです。
しかし、障がいの内容や等級によっては、就職の難易度が変わることもあります。
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
身体障害者手帳を持っている方の中でも、軽度の障がい(等級が3級~6級程度)に該当する場合は、就職が比較的スムーズに進むことが多いです。
これは、企業側が配慮しやすく、通常の業務に支障が少ないと判断されるためです。
特に、軽度の上肢障がいや視力障がいなど、デスクワークに影響が少ない障がいの場合、一般の事務職やIT関連の仕事など、幅広い職種での採用が期待できます。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
身体障がいは、外見や診断書の情報から企業が状況を把握しやすく、どのような配慮が必要か明確にしやすいのが特徴です。
そのため、企業側も安心して採用を進めやすい傾向があります。
例えば、車いすを使用している場合、バリアフリーのオフィス環境を整えることで対応できます。
また、聴覚障がいの方には筆談やチャットツールを活用することで、業務に支障が出にくくなります。
企業側が合理的配慮を明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
合理的配慮とは、障がいのある方が働きやすい環境を提供するために企業が行う対応のことです。
身体障がいの場合、具体的な配慮がしやすいため、企業も受け入れに前向きになりやすいです。
例えば、バリアフリーのオフィスでの勤務や、通勤時間の調整、手話通訳者の配置などが挙げられます。
こうした配慮が整っている企業では、身体障がいを持つ方が長く安定して働ける環境が整っていることが多いです。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
一方で、上肢や下肢に重度の障がいがある場合は、通勤や作業に制約が生じることがあります。
そのため、完全在宅勤務が可能な求人や、特定の業務に特化したポジションを探す必要があります。
特に、製造業や営業職など、身体を動かす仕事では採用が難しくなるため、デスクワーク中心の職種を選ぶことが重要です。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
身体障がいがあっても、コミュニケーションに問題がなければ、一般職種への採用のチャンスが広がります。
特に、電話対応や対面での接客が求められない事務職や、IT系の仕事では、障がいの影響が少ないため、採用の可能性が高まります。
PC業務・事務職は特に求人が多い
身体障がいのある方の中でも、特に事務職やPC業務の求人は多くあります。
データ入力、経理、総務などの仕事は、障がいの影響を受けにくく、企業側も採用しやすい職種の一つです。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
精神障害者保健福祉手帳を持つ方の就職は、身体障がい者とは異なる課題があります。
精神障がいは外見からは分かりにくく、症状の波があるため、企業側が受け入れに慎重になるケースが多いです。
また、合理的配慮が必要な場合でも、企業側がどのように対応すればよいか分からず、採用を控えることもあります。
そのため、精神障がい者の方がdodaチャレンジで求人を紹介してもらえないと感じることがあるのです。
次の項目では、精神障がい者の就職事情と、紹介が難しい理由について詳しく説明します。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障がいや発達障がいを持つ方の就職において、企業側が特に重視するのは「症状の安定性」と「長く働き続けられるかどうか」です。
精神障がいの症状は日によって変動しやすく、ストレスや環境の変化によって悪化することがあります。
そのため、企業側は「安定して働けるかどうか」を重要視し、面接時にも確認されることが多いです。
また、継続的に働ける環境を提供できるかどうかを判断するため、過去の職歴や退職理由について詳しく聞かれることがあります。
転職回数が多い場合は、「なぜ辞めたのか」「どのような環境なら続けられるのか」を整理し、面接で伝えられるように準備しておくことが大切です。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障がいや発達障がいは、外見からは分かりにくいため、企業側が「どのように対応すればよいのか分からない」と不安を抱くことが多いです。
例えば、統合失調症やうつ病の方が応募した場合、企業側は「ストレスのかかる場面でどのような対応が必要なのか」「どの程度の配慮が求められるのか」が分からず、採用に慎重になることがあります。
また、発達障がいの方の場合、コミュニケーションの取り方や仕事の進め方に独自の特性があるため、企業側が適切な配慮を提供できるかどうかを判断しづらいこともあります。
そのため、応募者側から「このような配慮をいただけると働きやすいです」と具体的に伝えることが大切です。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
精神障がいや発達障がいを持つ方が就職を成功させるためには、採用面接での「配慮事項の伝え方」が非常に重要です。
企業側は「この応募者を採用した場合、どのような対応が必要になるのか」を知りたいため、漠然と「配慮してほしい」と伝えるのではなく、具体的な内容を説明することが求められます。
例えば、「集中力が続きにくいので、短い休憩を挟みながら働ける環境だとありがたいです」「電話対応が苦手なので、主にメールでのやり取りができる業務が望ましいです」など、自分の特性と希望する配慮をセットで伝えると、企業側も採用を前向きに検討しやすくなります。
また、自己PRでは「どのような環境ならパフォーマンスを発揮できるのか」をしっかりアピールすることが重要です。
「過去の職場で工夫して乗り越えたこと」や「どのような業務なら得意なのか」を伝えることで、企業側の不安を和らげることができます。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
療育手帳(知的障害者手帳)を持つ方の就職事情は、精神障がいや身体障がいの方と異なる特徴があります。
療育手帳は、知的障がいの程度によってA判定(重度)とB判定(中軽度)の2つに分かれます。
判定の違いによって、一般就労が可能か、福祉的就労が適しているかが変わってきます。
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳の判定によって、選択できる働き方が変わります。
A判定(重度)の場合、一般企業での就労は難しいことが多く、就労継続支援B型(非雇用型)などの福祉的就労が中心となります。
一方、B判定(中軽度)の場合、一般就労が可能なケースも多く、企業側の合理的配慮を受けながら働くことができます。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定(重度)の方は、一般企業での就労よりも、福祉的就労の枠組みを活用することが一般的です。
就労継続支援B型では、雇用契約を結ばずに、働くためのトレーニングを受けながら、自分のペースで作業を行うことができます。
また、支援員が職場環境の調整を行ってくれるため、無理なく働けるのが特徴です。
将来的に一般就労を目指したい場合は、まず就労移行支援を利用してスキルを身につけ、A判定の方でも採用可能な企業を探していく方法があります。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定(中軽度)の方は、企業によっては一般就労が可能なケースも多く、適切なサポートを受けながら働くことができます。
例えば、単純作業や軽作業だけでなく、事務補助やデータ入力などの業務に従事することも可能です。
また、企業側が合理的配慮を提供することで、業務の範囲を調整しながら働くこともできます。
就職を成功させるためには、ハローワークや障がい者就労支援センターを活用し、自分に合った働き方を探すことが大切です。
障害の種類と就職難易度について
障がいの種類によって、就職の難易度は異なります。
一般的に、企業が合理的配慮を提供しやすい身体障がい者は就職しやすく、見えにくい精神障がいや発達障がいは採用のハードルが高くなる傾向があります。
また、知的障がい者の場合、療育手帳の判定によって就労の選択肢が異なります。
そのため、自分の特性を理解し、適した職種や働き方を選ぶことが大切です。
次の項目では、障がいの種類別の就職難易度と、それぞれの対策について詳しく解説します。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
障害のある方が仕事を探す際、「障害者雇用枠」と「一般雇用枠」のどちらで応募するべきか迷うことがあるかもしれません。
障害者雇用枠は、企業が法令に基づき設けている枠組みであり、障害に応じた配慮を受けながら働くことができます。
一方で、一般雇用枠は、障害の有無に関係なく、通常の採用基準で選考が行われる枠組みです。
それぞれの雇用枠の特徴について詳しく説明します。
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠は、「障害者雇用促進法」に基づき、一定の規模以上の企業が設けることを義務付けられている雇用枠です。
障害のある方が働きやすい環境を整えることを目的としており、企業側は配慮事項を考慮しながら採用を行います。
企業によっては、バリアフリーの環境整備、時短勤務の導入、特定の業務に特化したポジションの提供など、個々の状況に応じた支援を行っていることもあります。
障害の特性に合わせた働き方をしたい場合は、障害者雇用枠の活用が適しています。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
日本では、障害者の雇用促進を目的として「障害者雇用促進法」が定められています。
この法律では、一定の規模以上の企業に対し、全従業員のうち一定割合を障害者として雇用することを義務付けています。
2024年4月から、この法定雇用率が引き上げられ、民間企業では従業員の2.5%以上を障害者として雇用することが求められます。
障害者雇用枠での就職を希望する場合、この法定雇用率の引き上げにより、今後さらに多くの企業で障害者の採用が進むことが予想されます。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
障害者雇用枠では、応募時に障害の内容を企業に伝える「オープン就労」が基本となります。
企業は、応募者の障害特性や働き方の希望を聞きながら、適切な職場環境や業務内容を調整します。
例えば、「長時間の集中作業が難しいので、こまめな休憩を取りながら業務を行いたい」「車いすを使用しているため、バリアフリーの環境が必要」といった具体的な配慮事項を事前に伝えることで、無理なく働ける環境が整えられます。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠では、障害の有無に関係なく、すべての応募者が同じ基準で選考を受けます。
そのため、求められるスキルや経験、業務遂行能力において、他の応募者と同等の評価を受けることになります。
一般雇用枠で採用されると、特別な配慮を受けることなく、通常の職場環境で働くことが前提となります。
そのため、自分の障害特性によっては、業務の負担が大きくなることもあるため、慎重に判断する必要があります。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
一般雇用枠では、障害の開示は求められません。
障害のことを企業に伝えずに働く「クローズ就労」も可能です。
ただし、クローズ就労の場合、企業側は障害に関する配慮を行う義務がないため、業務の進め方や職場環境が自分に合わないと感じることもあります。
逆に、入社後に障害のことを伝えてしまうと、配慮が受けにくかったり、職場の理解が得られなかったりする可能性があるため、事前に十分に検討することが大切です。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠では、企業は特別な配慮を提供する義務がなく、通常の業務内容や労働条件での勤務が前提となります。
そのため、障害のある方が一般雇用枠で働く場合は、自分で業務の調整を行う必要があるかもしれません。
また、障害による業務の制限を理由に、仕事の評価が下がる可能性もあるため、自分の適性や業務遂行能力を正しく見極めることが重要です。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障害者の雇用率は、年代によって異なる傾向があります。
若年層では就職支援サービスや新卒枠の利用が可能ですが、中高年層では経験やスキルが求められるため、採用の難易度が変わってきます。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
厚生労働省の「障害者雇用状況報告(2023年)」によると、年代別の障害者雇用率には以下のような特徴があります。
若年層(20代〜30代)は、就職支援制度や新卒採用の枠を活用しやすいため、比較的スムーズに就職できるケースが多いです。
特に、企業の障害者採用枠を活用すれば、未経験でも採用される可能性があります。
一方で、40代以上の求職者は、即戦力としてのスキルや経験が求められることが多く、求人の選択肢が限られることがあります。
特に、長期間のブランクがある場合や、前職での業務経験が活かせない場合、就職が難しくなる傾向があります。
また、50代以上になると、定年が近づくこともあり、企業側が積極的に採用しづらくなることもあります。
そのため、年代ごとに適した就職活動の方法を考え、スキルアップやキャリアプランを意識することが大切です。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。
未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。
経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
20代〜30代の障がい者求職者は、企業にとってポテンシャルが高く、将来的な成長を期待されやすいことから、比較的採用されやすい傾向にあります。
特に、未経験からのチャレンジが可能な職種や、研修・育成制度が整っている企業では、若年層の採用が積極的に行われています。
また、障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の引き上げにより、企業は障がい者を積極的に採用する必要があり、20代〜30代の求職者には多くのチャンスがあります。
求人数も豊富で、事務職やIT関連職、接客業など、さまざまな業界で採用枠が用意されています。
ただし、若年層の場合は「実務経験が少ない」「社会人経験が浅い」といった課題があるため、就職活動を成功させるためには、履歴書・職務経歴書の作成や面接対策をしっかり行うことが重要です。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代以降の障がい者雇用は、若年層に比べてやや難易度が高くなる傾向があります。
その理由として、企業側が即戦力を求めるケースが増えるため、スキルや経験の有無が採用の大きなポイントになることが挙げられます。
特に、未経験の職種に応募する場合は厳しくなるため、これまでの職務経験を活かせる分野を中心に就職活動を進めるのが得策です。
例えば、事務職や営業職、専門職など、過去の経験が役立つ職種に応募すると、採用の可能性が高まります。
また、40代以降の求職者は、長期的なキャリアプランを見据えたうえで、自分に合った働き方を模索することが大切です。
ハローワークの職業訓練や、就労移行支援を活用してスキルアップを図るのも一つの方法です。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代以上の障がい者求職者は、企業側の採用基準が厳しくなる傾向にあります。
特に、体力的な負担が少ない事務職や軽作業系の仕事が中心となり、フルタイム勤務よりも「短時間勤務」「特定業務に特化した職種」などの求人が多くなります。
また、企業側としても、50代以上の求職者を採用する場合は「これまでの職務経験」「長期的に働けるかどうか」といった点を重視するため、スキルや経験があると有利に働きます。
そのため、50代以上の方は、過去の経験を活かせる職種に応募することに加え、求人の選択肢を広げるために、就労移行支援やキャリア相談を活用するのがよいでしょう。
さらに、短時間勤務やパート勤務など、柔軟な働き方を検討することも、選択肢を増やすポイントになります。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
dodaチャレンジをはじめとする障がい者向け就職支援エージェントには、基本的に年齢制限はありません。
しかし、実際には「50代前半まで」がメインターゲット層とされることが多いです。
これは、企業側が求める人材の年齢層や、求人の種類による影響が大きいためです。
例えば、若年層はポテンシャル採用の枠がある一方で、50代以上になると「経験・スキルがあるか」「長期間働けるか」といった点がより厳しく問われる傾向にあります。
そのため、50代以上の求職者がdodaチャレンジを利用する際は、過去の職務経験を活かせる求人に絞って応募することが重要です。
また、障がい者雇用の専門エージェントだけでなく、公共機関のサービスも併用すると、選択肢が広がる可能性があります。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
50代以上の求職者や、一般の転職エージェントでは紹介が難しいケースでは、ハローワークの障がい者窓口や、障がい者職業センター(独立行政法人)が大きな支援になります。
ハローワークの障がい者窓口では、障がい者専用の求人情報を提供しているほか、職業訓練の紹介や面接対策のサポートも受けられます。
障がい者職業センターでは、職業適性診断や職業訓練を通じて、適職探しをサポートしてくれるため、利用する価値があります。
また、ハローワークでは「障がい者トライアル雇用制度」を活用することもでき、一定期間試験的に働きながら、企業との相性を確認することが可能です。
これは、年齢が高い求職者にとっても、実際の職場環境を試す良い機会になります。
このように、dodaチャレンジなどの民間の転職エージェントと、ハローワークや障がい者職業センターといった公共機関を組み合わせて利用することで、自分に合った就職先を見つける可能性を高めることができます。
dodaチャレンジで断られたときの対処法について|よくある質問と回答
dodaチャレンジを利用する際、求人を紹介してもらえなかったり、面談後に連絡がなかったりするケースがあります。
これは、希望する職種や条件、スキルの有無などが影響していることが多いです。
しかし、対策を取ることで、より良い仕事に出会うチャンスを広げることができます。
ここでは、dodaチャレンジで断られた場合の具体的な対処法について、よくある質問をもとに解説していきます。
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの口コミには、「キャリアアドバイザーが親身に相談に乗ってくれた」「障がい者雇用の専門的な知識があり、的確なアドバイスをもらえた」などの良い評価がある一方、「希望する求人が見つからなかった」「条件に合う仕事がなかった」などの意見もあります。
特に、スキルや職歴が少ない場合、希望条件が厳しい場合などは、紹介できる求人が少なくなる傾向にあります。
口コミを参考にしながら、自分に合った転職サービスを選ぶことが大切です。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジで求人を紹介されなかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
まず、なぜ断られたのかを明確にし、それに対する対策を取ることが重要です。
例えば、「スキル不足」が理由の場合は、ハローワークの職業訓練や就労移行支援を活用し、必要なスキルを身につけるとよいでしょう。
また、「希望条件が厳しすぎる」と言われた場合は、勤務地や勤務形態を少し広げてみるのも一つの方法です。
さらに、dodaチャレンジ以外の障がい者向け転職エージェント(atGP、リクルートスタッフィング、アットジーピーなど)や求人サイトも併用することで、より多くの求人情報を得ることができます。
関連ページ:dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
面談後に連絡がない場合、いくつかの理由が考えられます。
– 求職者の希望条件に合う求人が現在ない
– 担当アドバイザーが新しい求人を探している途中で、まだ案内できる案件がない
– メールが迷惑フォルダに入ってしまっている、または誤って削除してしまった
– アドバイザーの業務状況によって、連絡が遅れている
通常、面談後1週間以内に連絡が来ることが多いですが、2週間以上経過しても何も連絡がない場合は、一度担当者に問い合わせてみることをおすすめします。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・求人・内定それぞれのケースと連絡なしの理由
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、キャリアアドバイザーが求職者の状況を詳しくヒアリングし、それに基づいて求人を紹介してくれます。
面談の流れは以下のようになります。
1. これまでの職歴や経験の確認
2. 障がいの種類や配慮事項についてのヒアリング
3. どのような仕事を希望しているか(業種・職種・勤務形態など)
4. これまでのスキルや資格、得意なことの確認
5. 求人紹介の可否についての説明
特に、障がいの特性や職場で必要な配慮事項については、しっかりと伝えることが重要です。
事前に自己PRや職務経歴を整理し、履歴書・職務経歴書を準備しておくと、スムーズに面談を進めることができます。
関連ページ:dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がいを持つ方々が就職を支援するためのサービスです。
特に障がい者向けに、適切な職場を見つける手助けを行っています。
サービスの特徴として、障がいに配慮した求人の紹介、面接対策、就職後のサポートが挙げられます。
専門のアドバイザーが一人一人に合ったアドバイスを行い、マッチング精度が高いため、利用者の多くが納得できる職場に就職しています。
さらに、オンライン相談も可能で、場所に縛られず利用できる点が便利です。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジは、障がい者手帳を持っていない方にも利用可能です。
障がい者手帳がなくても、身体的・精神的な障がいがあればサービスを利用することができます。
自分の障がいの状態に合った就職支援を受けることができ、企業に対しても、個別にサポートを提供してくれます。
手帳を持っていない方でも、悩みや不安に寄り添い、適切なアドバイスをもらえるため、安心して利用できます。
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジは、多くの障がいに対応していますが、一部の障がいについてはサービスが難しい場合もあります。
例えば、極度に重度の障がいがある場合や、専門的な支援が必要な場合などです。
しかし、個別のニーズに応じた対応をしているため、まずは相談することが大切です。
障がいの程度に応じて、必要なサポートが提供される場合もありますので、気軽に問い合わせてみると良いでしょう。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジの退会手続きは簡単に行うことができます。
公式ウェブサイトから手続きを進めることができ、必要な情報を入力するだけで退会することができます。
また、電話やメールで直接サポートに連絡することもでき、スタッフが手続き方法を案内してくれるので、安心して退会できます。
退会後は、再度サービスを利用したい場合でも再登録が可能です。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、オンラインでも受けることができ、全国どこからでも利用可能です。
自宅にいながら専門のカウンセラーと相談できるため、場所を選ばず自分のペースで進めることができます。
また、対面でのカウンセリングも各支援センターや相談窓口で受けることができ、直接相談したい方にも対応しています。
どちらの方法でも、就職活動を効果的に進めるためのアドバイスを受けられます。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジに年齢制限はありません。
障がいを持つ方であれば、年齢に関係なくサービスを利用することができます。
若年層からシニア世代まで、幅広い年齢層の方々が利用しており、それぞれに合った求人を提案してくれます。
年齢に関わらず、自分に合ったキャリアを見つけるためのサポートを受けることができるので、安心して利用できます。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは、離職中の方でも利用することができます。
障がいを持つ方々に向けて、再就職支援を行っているサービスです。
離職後に就職活動を再開したいと考えている方に、求人情報の提供や面接対策、企業とのマッチングをサポートしてくれます。
離職中でも、キャリアに合ったサポートを受けながら、安心して新たな職場を探すことができます。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは、学生でも利用可能です。
特に卒業を控えた障がいを持つ学生に向けて、就職活動のサポートを提供しています。
求人情報の提供や面接対策、就職後のサポートが充実しており、学生の就職活動を支援します。
自分の障がいに配慮した職場を見つけることができ、就職活動をスムーズに進めるための手助けを受けることができます。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスとの比較一覧
dodaチャレンジは、障がい者雇用に特化した転職エージェントであり、求職者一人ひとりの希望や特性に応じた求人紹介を行っています。
従来のエントリー型求人サイトとは異なり、キャリアアドバイザーが間に入り、企業の要望や職場環境をしっかり把握した上で紹介するため、応募後に断られるリスクを減らすことが可能です。
また、履歴書の添削や面接対策など、選考通過率を上げるためのサポートも充実しており、就職活動が初めての方でも安心して利用できるのが特徴です。
他の障がい者就職サービスと比較しても、dodaチャレンジは企業との交渉力が強く、求職者の希望と企業の条件を上手に調整してくれるため、選考が進みやすいと評価されています。
また、障がい者雇用に配慮のある職場の求人を多数保有しているため、応募後のミスマッチが少なく、安心して応募できるサービスとして支持されています。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や対処法|難しいと感じた詳しい体験談まとめ
dodaチャレンジで断られる理由にはいくつかのパターンがあります。
まず、求人企業が求めるスキルや経験に合致していない場合や、選考のタイミングが遅れてしまい、ポジションが埋まっていた場合などが挙げられます。
また、障がい者雇用枠の求人は限られているため、応募者の希望する条件に合う企業を見つけることが難しい場合もあります。
その結果、企業側が選考を進めるのが難しいと判断し、断られることがあるのです。
このような状況に対応するには、キャリアアドバイザーに相談し、履歴書や職務経歴書を再度チェックしてもらうことが大切です。
応募する求人ごとに内容を調整し、企業が求めるスキルや経験に合ったアピールポイントを加えることで、選考通過率が上がる可能性があります。
また、応募前に企業や業界の情報をしっかり調べ、自分の希望条件を見直すことも有効です。
dodaチャレンジではキャリアアドバイザーが具体的なアドバイスを提供してくれるため、それを参考に次のステップを考えると良いでしょう。